先生たちのポートフォリオ
- 2月9日 幼児の自然体験型保育の研修会 子どもたちに自然の良さや大切さをどう伝えたらいいのかな?
-
2023.02.21
- 2月3日 通園バス運行等についての危機管理研修会
-
2023.02.13
今回の研修では「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」「運行管理と点呼について」「乗客の車内への置き去り防止に向けた取り組みについて」のテーマで国土交通省、近畿運輸局から説明を聴き、危機管理について学びました。本園では、バスの添乗に関わるマニュアルを作成し、バスの安全な運行に努めていますが、この研修を通してより見つめ直すことが必要であると感じました。園児が安心して通園バスを利用し、事故を起こさない安全な運行となるように職員と運転手で連携していきたいです。
【磯﨑 他1名参加 場所:私学会館】
- 1月26日 食物アレルギーの知識 エピペンの使い方実習も
-
2023.02.06
かめさきこどもアレルギークリニックの院長先生から、なぜ食物アレルギーがおこるのか、どのようなアレルギーがあるのかについて学びました。また、エピペンの使い方についても改めて確認する実習を行いました。園でも職員全員で万が一に使い方を確認、振り返りをし、食物アレルギーの知識を共有していきたいと思います。
【藤本:豊中市立人権平和センター豊中】
- 1月27日 新任研修 東豊中幼稚園の保護者(子育て)支援について(園内研修)
-
2023.01.30
今回の研修では、自園で実施している保護者支援について学んだり、ワークを通して他己紹介をしたり、ある事例について保護者の方へお伝えするという体験をしました。会話をする上で、その人との関係性や、取り巻く環境に配慮することや、相手の立場になって会話をするということが大切であると学ぶことができました。
今回学んだことを活かして、より良い関係性が作れるよう、実践していきたいです。
【名前 斉明寺 :他5名参加 :場所 東豊中幼稚園 】
- 1月23日 令和4年度幼稚園新規採用教員研修
-
2023.01.30
今回の研修では、子どもの安全と危機管理について学び、幼稚園における子どもの安全保障の重要性について再確認しました。セルフマネジメントでは、自己成長・確認シートを用いて自分自身の強みと弱みを分析し、2年目に向けての目標を設定しました。
子どもたちが安心し安全に過ごすことができるよう環境を整えたり、適切な配慮を行っていったりしたいと思います。
【名前 神野:他1名参加 :場所 大阪府教育センター】
- 12月22日 新任研修 チームで保育・仕事を進めていくには?(園内研修)
-
2022.12.26
今回の研修では、自分の大切にしている価値観について考え発表し合ったり、ワークを通して価値観の合意形成を体験しました。価値観の合意形成の難しさや、チームで仕事を進めていく上での価値観の尊重の大切さについて学ぶことができました。今回学んだことを活かして、職員全員でより良い保育ができるよう努めていきたいと思います。
【名前 松枝:他8名参加 :場所 東豊中幼稚園】
- 12月15日 子どもの食べる意欲につなげる食育
-
2022.12.20
今回の研修では、食べる意欲につなげる食育について学んできました。食事は健康だけでなく、人格形成にも影響を与えることから食事が楽しいことだと子どもが感じることが何よりも大切であること、食事中の水分量や足がしっかり地面についていることが嚙む力に関わっていることなども学びました。子どもの好き嫌いを受け止め、できることから食生活の改善に挑戦し、楽しい食事ができるように心がけ、子どもの食べる意欲を育てていきたいと思います。
【藤田 豊中市立人権平和センター豊中】
- 10月28日 園内研修
-
2022.12.13
今回の園内研修では2学期(9、10月)の保育環境を振り返り、また他クラスの保育環境を見て、11月以降からの保育室や自由遊びでの幼稚園全体の環境をより良くするため、グループに分かれて話し合いをしました。図に書いたり、話し合いをしたりすることで見えてきた課題を改善し、子どもたちが楽しく、安全に過ごせる環境を作っていきたいと思います。
【名前 岸間 :他30名参加 場所:遊戯室】
- 12月8日 令和4年度 幼児教育アドバイザーフォローアップ研修B
-
2022.12.12
「ファシリテーターの意義と役割・園内研修の企画・立案【検証】」
今回の研修では、実際に行った園内研修の実践レポートをもとに小グループ内で発表し合い、行ってみて気付いたことをまとめました。まとめたことで、実際に行ってみて良かった点や課題、今後取り組みたいことなどにより気付くことができました。今回の研修での気付きを活かした園内研修を行えるように努めていきたいと思います。
【馬場 他2名参加 場所:大阪府教育センター】
- 12月2日 研修名:新任研修「ストレスとの上手な付き合い方 自分のココロに問いかけてみよう!」
-
2022.12.06
今回の研修では、自分のストレスサインを知るためにワークを通してストレスチェックを行ったり、セルフケアの1つであるストレッチワーク(副交感神経を高めるトレーニング)を体験したりしました。
ストレスと上手くつきあっていくことができるよう、今回学んだことを活かし、自分に合ったストレスケアを見つけていきたいと思います。
【名前 神野:他4名参加 :場所 東豊中幼稚園】
- 11月22日 研修名:令和4年度 幼稚園新規採用教員研修(第7回)
-
2022.12.01
今回の研修を通して、日本では様々な人権課題を抱えているということを改めて理解し、教員としてどのようなことを意識して環境づくりに努めていくかについて、考えることができました。子どもの人権を守るためには、一人ひとりの子どもの想いや気持ちを尊重し、ありのままの姿でいられる環境づくりが大切だと学びました。
今後も教員として、子どもたちが安心して過ごせるような保育を行いたいと思います。
【名前 松下:他2名参加 :場所 大阪国際センター(ピースおおさか)】
- 10月26日 研修名:幼稚園新規採用教員研修 第6回
-
2022.11.16
今回の研修では、カウンセリング理論を深め、相手との関わり方や、学級経営の在り方について学びました。
相手が抱えている「困り」が何か、そして何が原因なのかを会話の中から見つける事の大切さ、また幼稚園と言う場所が社会生活の一歩であるという意識を再確認できました。
今後も子どもや保護者と関わる中で困っている事に対し、より関係を深めていけるよう努めていきたいです。
【名前 斎明寺:他4名参加 :場所 東豊中幼稚園/大阪府教育センター】
- 10月31日 新任研修 子どもの姿を文章で発信してみましょう!(園内研修)
-
2022.11.07
今回の研修では、自身の保育のねらいや活動内容、子どもの様子や成長したことを捉え、文章にまとめて発信する方法を知りました。
文章にまとめる際、一番伝えたいことを明確にすることが大切だと学びました。さらに、子どもたちの心情や言動を書くとより深くわかりやすい文章になることがわかりました。
今後、グループに分かれて実際に園からのおたよりを書いてみる際に、今回学んだことを活かしていきたいと思います。
【名前 髙橋:他4名参加 場所 東豊中幼稚園】
- 9月28日 ファシリテーション・リーダーシップ講座『問題解決と出会う』
-
2022.10.21
今回の研修では、どのようにしたらよいのだろう…とHOWの問いかけをするのではなく、何が必要なのか…とWHATの問いかけをすることや、思い込みや推察などではなく事実と真実を整理することなど、問題解決の方法をワークショップを取り入れながら体験実感することができました。全5回の研修で学んだ“ファシリテーション”を自分なりに使いながら身に付けて、同僚との対話の中で用い、チーム力を高めながらより良い保育ができるよう努めていきたいと思います。
【藤本 他2名参加 場所:大阪私学会館】
- 10月11日 研修名:令和4年度 新規採用保育者研修会
-
2022.10.19
今回の研修では、自分の行動を振り返り、良い面と改善が必要な面を整理することができました。また、グループ内での意見共有を通して、他の人がどのようなことを大切にし仕事に取り組んでいるのかということを知ることができ、良い刺激を受けました。
今回学んだことを活かし、自分自身の行動の良さや改善点を意識化することができるよう、振り返ることを大切にしていきたいと思います。
【名前 神野:他1名参加 :場所 大阪私学会館】
- 10月5日 研修名:令和4年度 支援教育実践研修F(発達障がいに関する内容)
-
2022.10.19
今回の研修では、発達障がいのある子どもの教育に関する知識や技能についての認識を深めました。また、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高めました。
全ての子どもたちにとって安心・安全な保育環境にするためには、子どもに寄り添った支援やユニバーサルデザインを意識した環境づくりが必要であることを学びました。
今回学んだことを活かして、子どもと関わっていきたいと思います。
【名前 髙橋:他4名参加 :場所 東豊中幼稚園(オンライン)】
- 8月25日 豊中こども財団研修会 「新任職員を育成するリーダー職員の役割」
-
2022.10.05
新任職員を育成するリーダー職員の役割として、まず職場で大切にしている「チームワーク」「同僚性」等を意識しながら指導方法を考えていくことが重要だと学びました。
一方的に伝えるのではなく「対話」をしながらお互いに学習できる職場の環境作りをしていくことでよりチームワークが強まると感じました。これからも園内研修や外部研修にも積極的に参加し、職員同士で高め合い支え合う組織文化を作っていきたいと思います。
【名前:西坂 :他24名参加 :場所 東豊中幼稚園】
- 9月27日 新任研修 子どもの姿を捉えてみよう(園内研修)
-
2022.10.05
今回の研修では、子どもたちが遊びの中で何を学び、楽しさを感じているか等、様々な視点から子どもを見つめ、幼児理解を深めることができました。
また、子どもたちの遊びの様子を映像で視聴し、その場面での子供の気持ちや遊び方について感じたことを意見交流することで、今後の環境構成を改めて考えることもできました。
今回学んだことを活かし、日々の子どもたちの姿をヒントに、子どもだけで遊びを展開できるような環境作りに努めていきたいと思います。
【名前:松下 :他5名参加 :場所 東豊中幼稚園】
- 9月26日 令和4年度 保育技術専門研修F「すべての子どもが安心できる場をー気持ちを伝えよう!ー」
-
2022.09.29
今回の研修では、子どもが安心して気持ちを出し合える場をつくるための具体的な取り組みや、小学校における「ひらがな学習」の工夫について学ぶことができました。また、幼稚園での「ふつう」「あたりまえ」についても考え、理解を深めることができました。今回学んだことを活かして、幼稚園が子どもたちの安心の場となるよう、声かけや環境づくりに努めていきたいと思います。
【松枝 大阪府教育センター】
- 8月30日 令和4年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座
-
2022.09.13
「第4回 リーダーシップと出会う」
今回は、リーダーにはどのような資質能力が求められるのかや、リーダーの役割について考えたり、自分自身はどういったリーダーとしての強みがあるのか、リーダーシップの様々な方法などについて教えていただいたりしました。
いろいろな立場や年齢の保育者とチームで仕事をしていく上で、今回学んだことを活かし、リーダーシップを発揮しながら、より良い保育をみんなでつくりあげていきたいと思います。
【辻本:他2名参加 大阪私学会館】
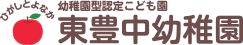

講師の先生による年中児との自然の中でのあそびと学びの公開保育の後、他園の先生方とグループディスカッション、そして参加者の自然体験というとても実りある1日研修でした。自然の匂いを嗅ぐ、自然の音を聴く、自然に触れるばど、様々な活動を通して、自然も生きていることを感じる保育・研修でした。自園でも、園庭の環境を活かし、子どもたちと共に自然を感じることができるあそびや活動を取り入れていきたいと思います。
【藤本:他1名:学校法人ひまわり幼稚園】