先生たちのポートフォリオ
- 8月2日 第68回 幼児教育大講習会~ひかりのくに~
-
2019.09.04
- 8月2日 第68回 幼児教育大講習会~ひかりのくに~
-
2019.09.04
『こんなに楽しく、簡単にできる、子どもの主体の保育』
この研修では、子どもの主体の保育について、様々な事例を通し、具体的に学ぶことができました。また、「大人の受容的、肯定的、応答的にかかわられた子どもはその後の発達がよい」ことも学びました。これからの保育でも、子どもを第一に考え、温かく受け止めながら自己肯定感を育てていきたいです。
【大野 他14名参加 中央公会堂】
- 8月1日 幼稚園新規採用教員研修
-
2019.09.03
『人権について考える』
今回の研修では「人権」について学びました。同和問題、在日外国人問題、障がい者問題、男女平等、性的マイノリティ、いじめ問題など、あらゆる問題を通して、生命の尊さに気づき、自分自身を大切にすると共に人の気持ちを思いやる心をもたなければいけないと改めて感じました。保育者は、子ども一人ひとりを尊重し、お互いを大切にし合う態度や行動を育成できるよう支援していきたいと思います。
【岸間 他5名参加 大阪人権博物館】
- 7月31日 夏のチャイルドセミナー
-
2019.09.03
『準備のいらないラクラク工作術』
今回の研修では、身近にある素材を使い、作ったあとに遊べて子どもたちと楽しめる準備のいらない工作術について実際に体験し学びました。実際に作って遊んでみて自ら感じた「楽しい・もっと色々なものを作ってみたい」という体験を子どもたちと一緒に共有できるように身近にある素材を使った工作を取り入れていきたいです。
【寺口 他7名 大阪スカイビルタワーウエスト3階ステラホール】
- 7月31日 夏のチャイルドセミナー
-
2019.09.03
『今日がはじめの一歩』
今回の研修では、有名な童謡を作曲されている新沢としひこさんが目の前で「はらぺこあおむし」や「にじ」などを歌ってくださったり一緒に体を動かして踊ったりしました。音楽は教えるのではなく一緒に楽しむものとあらためて学びました。また、子どもたちが「楽しかった」と感じてもらえるような音楽や遊びを日々の保育に取り込んでみたいと思います。
【万 他8名参加 梅田スカイビル】
- 7月31日 夏のチャイルドセミナー
-
2019.09.03
『小学校までに育ってほしい学びの姿』
数字では表すことのできない、幼児期に身につけておくべき非認知能力(やりぬく力、協調性、忍耐力など)を園生活の中で子どもたち一人ひとりに育てていくことの大切さについて改めて学びました。また、今日の講演をきいて東豊中幼稚園の教育方針の3本柱(①自分で考えて決める力②思いやりをもって人と関わる力③自分を大切に思う心)に沿った保育は、子どもの育ちにとってとても重要であることを再確認し、これからも全職員で丸となって子どもの将来に繋がる保育をしていきたいと思います。
【正井 他7名参加 梅田スカイビルステラホール】
- 7月29日 災害時の救急処置と学校対応
-
2019.09.03
スポーツや外傷時、また学校園での事故や災害発生時に迅速かつ適切な応急手当の処置を学びました。止血法、人が倒れた時の手当、包帯法、傷病者の搬送や骨折時の固定法、災害救護時のシュミレーションを実技をもって体験して、救急処置の知識を深めました。目の前にある全ての命を平等に守ることに努めたいですが、いざ大きな災害に遭った時、起きている状況に応じて周囲の安全確認をして落ち着いて行動することが大切です。学んだことを職員間で共有しあい、活かしていきたいです。
【磯﨑 府立たまがわ高等支援学校内大阪体育研修センター】
- 7月25日 発達支援・障害児支援者対象研修会第2回
-
2019.09.03
『子どもの基本的生活習慣の確立や遊びを通した発達支援』
子どもたちは、自らの経験を基にして、周囲の環境や人との関わりの相互作用を通じて、様々な生活習慣を確立させていくことについて学びました。座位の保持、食事、更衣、どの生活習慣においても環境や人との関わりから、新しい情報を身体で感じ、変化に合わせて、身体の使い方を知り、覚えていく過程が、子どもの育ちにつながるように思いました。子どもたち自身が色々なものに触れ、感性豊かな育ちにつながるよう保育していきたいと思います。
【小川 他4名参加 豊中すこやかプラザ】
- 7月25日 園内研修
-
2019.09.03
『保育環境について』
今日は職員全員で、保育環境の見直しを行いました。子どもが安心安全に遊べる環境、そして、たくさん考え、工夫し、成長できるような保育環境について話し合いました。これからも職員同士で意見を出し合いながら、より良い保育環境づくりについて考えていきたいと思います。
【正井 他25名参加】
- 7月29日 幼稚園新規採用教員研修
-
2019.09.03
『リズム運動』
講義を受けるまでは、「リズム運動は、難しい」と思っていましたが、先生の動きを真似して楽しく踊れました。さらに先生は、平、ひざ、足、肩、等からだのパーツの動きを考えて組み合わせることで、自分のオリジナルリズム運動が作れることを教えてくれました。保育の中で、子どもたちと一緒に考えて、楽しいリズム体操も新たに取り入れたいと思います。
【万 他5名参加 大阪府教育センター】
- 7月22日 幼稚園新規採用教員研修 第3回
-
2019.08.02
今回は「児童虐待の現状と課題」と「食育・食物アレルギーへの対応」について学びました。児童虐待については、虐待の種別や対応について理解を深めることができました。子どもの安全を守るために迅速な対応や様々な機関との連携が求められることを知り、日々子ども達や保護者の変化に気付き見守ることが大切だと感じました。
食物アレルギーについては、ヒヤリハットの事例を通して、改めてアレルギーは命に大きく関わることだと知りました。園での給食や預かり保育のおやつ提供など日頃から気をつけていきたいと強く思いました。
【安田 他5名 大阪府教育センター】
- 7月12日 幼児教育アドバイザー育成研修 第3回目
-
2019.07.24
「非認知的能力」の重要性とそれを育む援助及び、カリキュラム・マネジメント
今回の研修では、非認知的能力の大切さ、それを育む援助方法を学びました。非認知的能力とは、算数や国語などの学習における知的な能力ではなく、気づく力ややりぬく力、人間を理解し、関係を調整する力など教えるのではなく、様々な体験を通して育っていく力です。そのような力が育めるよう、子どもたちが自分自身で考えて、意欲を持って取り組める環境を、これからも整えていきたいと思います。
【高井 他2名 大阪府教育センター】
- 7月3日 豊私幼設置者・園長研修会
-
2019.07.09
今回の研修を通して、支援教育や支援のポイントについて知り、知識を深めることができました。また、努力を認めること・ほめることや、肯定文で話す事の大切さを再確認することができました。これからも日々の保育でこれらのことを大切にしながら過ごしていきたいと思います。
【馬渕 他5名 リッツカールトン・大阪】
- 7月1日 就学前人権教育研究協議会A
-
2019.07.05
今回の研修では「人権基礎教育」「親学習」「マイノリティ」について学びました。他人を大切にする心、生命の尊さを理解し、子どもに伝えることが大切だと思いました。また、保護者の方が子育てをしていく上での悩みや不安を共有し合える「親学習」は、「自分だけではないのだ」と少しでも安心できるとても良い環境だと感じました。研修を受けて、保育者は子ども一人一人を尊重し、保育をしていくことが大切だと学ぶことができました。
【西坂 他5名 大阪府教育センター】
- 6月17日 子どもの発達や障害についての基礎知識
-
2019.06.28
今回の研修では、発達障害について学びました。発達障害といっても人によってそれぞれ特徴は異なり、個々に合わせた支援方法を考えていかなければいけないと感じました。今回は具体的な事例を取り入れながらの研修だったため、普段の保育の様子と置き換えて考えることができました。また、集団に入って活動をすることが全てではなく、その子自身が安心して過ごせるような環境づくりや支援について考えていきたいと思いました。この研修では、発達障害の基礎について改めて学びましたが、これからもまだまだ学び、日々の保育に役立てていきたいと思います。
【 三木 他6名 豊中人権まちづくりセンター】
- 6月18日 園所の危機管理体制の改善~防災教育を進めるために~
-
2019.06.27
園所の危機管理において災害が起こる前に出来る限りの防災をしておくことが重要だと感じました。また職員間で防災の取り組みについて確認や情報共有をし、災害があったときに適切な判断ができるようにしておきたいと思います。そして何より、子どもたちの命を守ることを第一に考えて保育者として冷静に行動したいと思います。
【松山 他1名参加 大阪府教育センター】
- 6月18日 新任研修交流会
-
2019.06.27
今回は、新任の職員が交流を深める研修として参加させていただきました。他の人の話を聞き、自らを振り返り自らを見つめ直すことができました。また、他の人の意見から自分に欠けているところを知り、共に解決策を考えることができました。意見を伝え合うなかで、気づかなかったことが多く、学んだことを日々の保育で実践していきたいと思います。日々自分の行動を振り返ることでより良い保育ができ、自分自身も成長できると感じました。
【佐々木 他2名参加 豊中市文化芸術センター】
- 6月15日 豊中子ども財団 A研修
-
2019.06.21
『こどもの育ちと造形活動』
今回の研修では、乳幼児期に造形活動について学びました。子どもの絵を見るときに、結果だけを見るのではなく、子どもが絵を描いている過程を見ることが大切だということを改めて感じました。また、子どもたちの「おもしろそう!」といった興味・関心を大切に「やってみたい!」と身体が動く造形活動を行っていきたいと思います。
【金 他17名 豊中市立文化芸術センター】
- 6月15日 豊中こども財団オーダーメイド講座「子どもが主役!」
-
2019.06.17
今回の研修を通して、一人ひとりの子どもを尊重すること(子どもが主役の保育)の大切さについて改めて学びました。また、そのためにはまず、子どもと関わる大人(保育者、保護者)自身が大事にされているという実感があることが重要であると知りました。
これからも子どもたち一人ひとりがもつ力を引き出し、丁寧に関わる中で、どの子どもたちも主役になれるような保育をしていきたいと思います。
【谷本 他10名 豊中市立文化芸術センター】
- いつでも・誰でもできる、緊急下のこころのケア
-
2019.06.14
『子どものための心理的応急処置』
今回、私たちは災害・事件に合った子どもたちの心のケアの手法を教えていただきました。被災・被害直後のメンタルのメカニズムを知る事で、冷静に支援を行える事がわかりました。特に被災した後は、衣食住の確保が何よりも大切でありPTSDを防ぐ事にもつながるそうです。また、早く日常を取り戻すことです。これを受け、幼稚園として出来る事は、保育者が同様せずに、被災後も保育が出来るかが重要となってくると思いました。子どもたちにとって安全と思える環境が災害後もすぐに作れるよう体制を考えていきたいと思います。
【平野 他2名 豊中市役所 第2庁舎3階 大会議室】
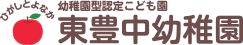

今回の研修を通して、乳幼児期の子どもへの関わり方は、今後の成長に大きく関わるものであり、とても重要であることを改めて学びました。身近な大人が、子ども一人一人の姿を受容し、肯定的に関わることで、子どもたちは認められることに喜びを感じ、より「やり遂げたい」という気持ちが芽生え、達成感や成功体験を増やしていくのだと考えます。これからの保育でも、子どもたちの些細な行動や言葉、好奇心の気持ちを大切にし、そこから一緒に保育を作っていきたいと思います。
【宝珠山 他14名 大阪中央公会堂】