先生たちのポートフォリオ
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅱ-2
-
2012.04.03

- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ-6
-
2012.04.03
「保育支援コーディネーターの役割とその専門性」
保育上、特別な支援が必要な子どもたちを支援するための調整役「保育支援コーディネーター」の役割について学びました。
支援の方法・方向性についての話し合いは関係者を中心とし、そこで決まった取組に全員で共通理解することの大切さを知りました。
日々の保育の中で職員全員で支え合い、保育の質を上げていく幼稚園づくりを大切にしたいと思います。
【浅田佑子】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ-4
-
2012.04.03
「子どもの不思議の世界を育む」~保育の中の科学遊び~
今回の研修では、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」「やってみたい!」という好奇心・探究心から自分なりの考えを試してみることで、新たな発見が生まれ、経験の積み重ねにより思考力が深まり、「学び」になることを学ばせて頂きました。
今後も、子どもたちの好奇心や探究心を大切にしていきたいと思います。
【馬場千尋】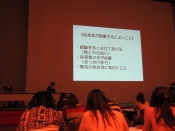
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ-3
-
2012.04.03
「学びをとらえなおす」
人が人間として育つ時代ごとの背景を踏まえ、現代社会の教育課題を明確にした上で『学び』について考えました。
学びの捉え直しとして、これまでの日本の学びは、教えるもの、授けるものと考え、どう分かり易く、上手に、効率よく指導するかの視点で考えられてきたが、話を聴く中で、学びの主人公である子どもが、どう学ぼうとしているのか、何を学んでいるのかに関心を向けていくことの重要性を感じました。
【井上啓子】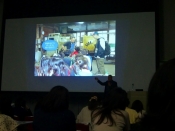
- 3月28日 大研大会 全体会
-
2012.04.03
「子どもと森へ出かけてみれば」
森で活動する子どもたちの写真を見ながら、子どもが子どもを生きている瞬間を感じ学びました。まだ知識がなく、大人の様に予測出来ない子どもが一つ一つに出会って感じる様々な経験を大切にしていきたいと思いました。
【佐原優子】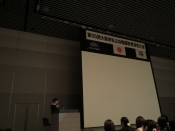
- 3月3日 園内研修
-
2012.03.11
今回私たちは、各保育室の環境設定について話し合いをしました。
各クラスの工夫している点を写真で見せ合い、より子どもたちが過ごしやすく遊びに夢中になれる環境かを見直しました。
子どもの視点に立ち、改めて保育室を見直す時間ができたのは、すべての職員が学びに繋がったと思います。
日々、子どもたちの様子に合わせた環境を整えていきたいです。
【平野 愛】

- 2月29日 東泉丘小学校授業参観
-
2012.03.01
2時間目の1.2.3年生、3時間目の4.5.6年生の授業を参観させていただきました。
卒園生たちの元気な姿、そして1年生が次の入学式で新一年生を歓迎する演技を見せて頂き、胸が熱くなりました。

- 2月28日 幼保小連携推進事業 第6回担当者会議
-
2012.03.01
今年度最後の会議でした。
小学校の授業内容を理解するとともに、幼・保での様々な活動等がどのような学びへと繋がっているのかを話し合いました。
次年度も幼・保・小の連携を深めていきたいと思います。 【右松・篠原】 (東豊中幼稚園において)

- 1月30日 府主催 就学前人権教育研究協議会
-
2012.02.02
今回参加した研修では、幼稚園・保育所・小学校間の「連携」について学びました。
例えば、年長の子どもたちが安定した状態で小学校に上がれるよう、幼稚園、小学校の職員が力を合わせなければなりません。このような連携に必要な信頼関係を強くするための具体的な活動も知ることができました。
保育所や小学校など様々な場所で子どもたちと関わっている先生方とのディスカッションを通して、幼稚園・保育所・小学校を繋ぐということは、今目の前にいる子どもたちを繋いでいくということなのだと思い、改めて「連携」の必要性を感じました。
【牧田茉里 2名参加】 (大阪府教育センター)

- 1月26日 東豊台小学校地域公開授業参観
-
2012.02.02
卒園生の成長が見れる参観日はいつも楽しみです。
今回も、高学年、低学年の時間に5名の職員が交代で参観させていただきました。

- 1月16日 豊中市幼保小連絡会
-
2012.01.30
ゆたか幼稚園、東豊中保育所、東豊台小学校、東豊中小学校、東泉丘小学校の先生方とともに、「さまざまな関わりの中で互いを大切にできる子どもに」をテーマに連絡会議が行われました。
この会議を通して、それぞれの園や学校での活動内容や子どもたちの姿を知ることができました。こうした話し合いで、様々な子どもたちの姿を理解し、今後子どもたちが幼児期の生活で経験したことや育んだことを小学生になったときに更に伸ばすことができるように、これからも連携を大切にしていきたいと思います。
【北川 和 (園長、連携担当者、年長担任)】 (ゆたか幼稚園)
- 1月14日 豊中市私立幼稚園連合会 研修会
-
2012.01.16
「幼児期に必要な体験をどの様に育んでいくか」
今回は、大妻女子大学教授の柴崎正行先生にお話を聞かせていただきました。
具体的な保育の実践方法や、子どもの姿の捉え方について教えていただき、保育を学び直すことができたと思います。
子どもが楽しかったと思えるような3年間、2年間を過ごせるように、私たち職員もさらに努力をしたいと思います。
【髙橋ちさと 全員参加】 (アクア文化ホール)
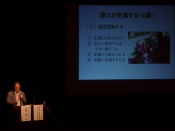
- 1月7日 園内研修
-
2012.01.16
本園から、海外研修に参加した教諭の報告を聞きました。
スウェーデンの子どものいる家庭への、国からの援助や幼稚園の保育環境を学ぶことができました。また、他国の保育を知ることができとても勉強になりました。今後の保育に活かせるよう、他国の保育にも関心を持ち、学んでいきたいと思います。
【鈴木絢子 全員参加】

- 12月21日 救急救命講習
-
2011.12.22
職員全員で救急救命講習を受講し、心肺蘇生法やAEDの使用法などを実技をしながら教えていただきました。傷病者に遭遇した際、救急車が到着するまでの5~6分に応急手当をしっかりと行えるかによって、助かる可能性のある命を救えるかどうかが決まってきます。いつでも勇気を持って行えるように、学んだことを常に新鮮な状態で覚えておきたいと思います。 【浅田佑子 全員参加】 (遊戯室にて)

- 12月17日 園内研修
-
2011.12.22
「構成論による読み書きの理論と実践」というテーマで研修を受けた職員が、発表を行いました。
子どもたちにとって、文字は身近なものですが、大人が教え込むのではなく、絵本を読んだり日常生活の中で、言葉の意味を読み取り、理解していくのだと学びました。
これからも、絵本の読み方を工夫したり、身近にある文字に触れながら、子どもたちの育ちに繋げていけたらと思います。 【山田奈津子】

- 12月8日 豊中市私立幼稚園連合会 園長設置者研修会
-
2011.12.22
今回は学校評価について研修を行いました。
- 11月25日 園内研修
-
2011.12.07
幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえた幼保小連携推進事業について、研究している内容を担当者が発表し、経過報告をしました。
また、年長児が地域の幼稚園・保育所・小学校と関わっている活動内容を、ビデオを通して見ることができ、年長児の担任だけでなく、職員全員で幼保小連携の取り組みについて、共通理解をすることができました。
【氏林美陽子】

- 11月27日 マニング博士セミナー
-
2011.11.30
「構成論による読み書きの理論と実践」
今回アラバマ大学バーミンガム校名誉教授で、構成論による読み書きの研究をされているマリアン・マニング博士の話を聞かせていただきました。
大人中心で読み書きのみを部分的に教えていく伝統的な教育ではなく、子ども中心で、意味、文法、読み書きの3つの側面をすべて使って、全体から部分へと教えていく構成論的な教育の素晴らしさを学びました。
【小石原雅子 4名参加】 (甲子園ノボテル)
- 11月16日 園内研修 (Christina Sales教授による勉強会)
-
2011.11.22
園で保育に取り入れている「パターンブロック」を研究し、そのフレームを考案、製作されているノーザンアイオワ大学のクリスティー教授に寄る研修を受けました。
実際に、私たちもパターンプロックを体験しながら、子どもに援助をする上で、子どもたちがパターンブロックを通して、どのような事を考え、どのような事に気づいているのかを知ることが大切だということを学びました。
パターンブロックの遊びを通して、より難しいフレームに挑戦したり、達成感を味わうことや、色々な形を移動させたり向きを変えることで形や角度の特徴に気づき、楽しめるように援助していきたいと思います。 【鈴木絢子】 (全員参加 園内にて)

- 11月15日 市議会議員団来園
-
2011.11.22
豊中市議会の議員さん方17名が、本園の保育見学に来られました。

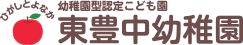

お辞儀、挨拶の仕方や、身だしなみなど、社会人としての行動について学びました。
いつも笑顔で元気よく話し、美しい身だしなみで機敏に動き、楽しむ心を持つことが大切だということで、「ニコニコ・ハキハキ・スッキリ・キビキビ・ウキウキ」を合言葉に向上心を持って毎日を楽しく過ごしたいと思います。
【木田梨恵】