先生たちのポートフォリオ
- 1月15日 私の『当たり前』を揺さぶろう~保育者に求められる人権感覚を育む~
-
2019.02.04
- 1月19日 豊私幼全体研修会
-
2019.02.01
今回の研修を通して、幼児教育の無償化について詳しく知ることができました。幼児教育の無償化に伴い、保育の質の向上が大切であるということを学びました。そのために、保育者は研修等を通して、キャリアアップをすることが大切だと思いました。
【馬渕 他11名参加 豊中市立文化芸術センター アクア文化ホール】
- 1月24日 食物アレルギー研修会
-
2019.01.28
『こどもの食物アレルギー対応とエピペン実習(食物アレルギーとエピペンについて~こども園での適切な対応~)』
今回は食物アレルギーの仕組み、アナフィラキシー等への適切な対応をアレルギーを専門とする医師から学びました。アレルギー症状に合わせて臨機応変な判断をするとともに、子どもたちの命を預かる保育者として常に危機管理をしていきたいと思います。また全職員が共通の認識をもち、子どもたちの命を守ることができるよう努めていきたいと思います。
【小川 他4名参加 豊中人権まちづくりセンター】
- 12月5日 豊中市食育研修会
-
2019.01.07
『子どもの心とからだを豊かに育む食育』
食育で何よりも大切な事は、食事の時間が楽しい、食べる事が嬉しいと思える環境をつくる事だと、感じました。その為に保育者や保護者の声かけであったり、時間の取り方が重要なのだと思います。大人になっても幼少期の食事の記憶は残ると言われています。給食の時間が子どもにとっても職員にとっても、楽しみになるよう考え、色々工夫していきたいです。
【篠原 他1名 豊中人権こどもセンター】
- 12月21日 食育体験会
-
2019.01.07
食育体験会でフライパン一つで作るじゃがもちと手作りジャムを作りました。ジャムは旬の野菜や果物を使って簡単に作ることができるので、年中組の子どもたちが育てた野菜を使ってジャムを作ることができることを実際に作って見せたいと思いました。子どもたちが「食」に興味がもてるような活動をこれからも考えていきたいと思います。
【藤田 他6名参加 ハグミュージアム】
- 12月6日 豊中こども財団研修
-
2018.12.14
『子ども・親・保育者が育つこれから求められる保育』
今回の研修では、改めて子どもをどのように見るのかということの大切さを感じました。子どものとる行動には、大人の考えもつかないような理由があることがあります。どのような時でも、子どもに寄り添うことのできる保育者でありたいと思いました。又、保護者の方々にしっかりと子どもの様子を伝えていけるよう今後もしていきたいです。
【高井 他4名参加 ザ・リッツカールトン大阪】
- 11月29日 発達支援・障がい児支援者対象研修会 第7回
-
2018.12.10
『発達支援・障がい児支援に係る社会資源』
豊中市における発達支援、障がい児支援についての現状や課題、具体的な取り組みについて知ることができました。支援者の「気づき」の意識は高まっている一方で「つなぎ、支える」についての知識や理解が不十分なことから具体的な対応に繋がらないケースがあると伺いました。今後もこのような研修を通して、よりスムーズに早期支援につなぐための知識を得て、すべての子どもが自分らしく、豊かに生きられるよう、専門職としてスキルアップし、園全体に共有していきたいと思います。
【谷本 他3名参加 すこやかプラザ】
- 11月27日 大阪府私立幼稚園連盟 ミドルリーダー教員研修会
-
2018.12.10
『組織を活性させるファシリテーティブな対話』
今回の研修でミドルリーダーとしての役割を学びました。園内のコミュニケーションが活性化するように、これまで同僚と話し合い築いてきた東豊中幼稚園の保育を後輩に伝えていくことや後輩が抱えている悩みに気付き相談しやすい雰囲気を作ることを今後意識していきたいです。
【松山 他1名参加 大阪私学会館】
- 11月22日 平成30年度幼稚園教育理解推進事業(大阪府協議会)
-
2018.12.06
『幼稚園教育と小学校教育との接続の推進について』
今回の研修では、大阪府内の校園所の方々の連携についての現状のお話をきくことができました。小学校も幼稚園も互いの連携をとても重要視しているものの、時間の取り方や継続する難しさ等の課題が多くあがりました。課題を解決できるよう、今回の話を参考に園の先生方と話し合いを重ね、自園で取り組んでいる小学校との連携を継続し、深めていきたいと思います。
【篠原 大阪府教育センター】
- 11月22日 平成30年度幼稚園教育理解推進事業(大阪府協議会)
-
2018.12.06
『幼稚園生活が幼児にとって安全なものとなるような環境の配慮や指導の工夫について考える』
他市のある園の”子どもにとって安全な環境”についての実践発表を聞いたあと、グループでそのテーマについて話し合いました。実践発表では、子どもが安心して夢中で遊び込む環境を作ることが、怪我の減少にも繋がるということを学びました。グループ協議では、避難訓練の実施の頻度や行い方の工夫などについて話し合いました。災害の多い現代、とても勉強になる協議でした。これからも子どもにとってどういった環境が安全面で、また楽しく遊ぶために適切であるかを日々考えながら過ごしていきたいと思います。
【天野 大阪府教育センター】
- 11月20日 障害児保育研修
-
2018.11.27
『子どものてんかんの対応~発作の見方とその対応の現状について~』
今回は、てんかんの原因・症状・対応について学びました。熱誠痙攣との違いを学んだり、薬の使用についても話を伺いました。幼稚園生活の中で万一、痙攣が起きた時も予備知識があるだけで、少しは落ち着いて対応できると思うので、今回の研修内容を園全体で共有し、安全管理に努めたいです。
【平野 他1名参加 豊中人権まちづくりセンター】
- 11月17日 豊私幼全体研修会 B研修
-
2018.11.27
『よりよいチームづくりを目指す、中核リーダーとしての役割を考える』
この研修では、中核リーダーの「しごと」や「チームへの関わり」等について、グループワークを通じて学び合うことができました。リーダーとしての資質や思想等も話し合い、様々な意見を聞く中で自分の考え方の幅も大きく広がりました。また、チームの関係性が話し合いを活性化させ、よりよい園づくりへと繋がることも学びましたので、これからも互いに学び合える関係性を職員全体で築いていきたいです。
【大野 他1名参加 豊中市文化芸術センター】
- 11月17日 豊私幼全体研修会 A研修
-
2018.11.27
『これからの保護者理解・保護者支援』
現代の子育て事情について知り、保護者の方がどのような不安や思いをもって子育てをしているのか学びました。様々な家庭の形があることを理解した上で私たち保育者がしっかりと、保護者の方と向き合い、信頼関係を築いていくことが子どもたちの心の成長に繋がっていくと思います。これからも家庭との連携を大切にしながら一緒に子どもたちの成長を見守り、その成長を保護者の方々と共に喜べる関係を築いていきたいと思います。
【正井 他11名参加 豊中市文化芸術センター】
- 11月10日 大阪幼児造形教育研究会 第8回研究大会
-
2018.11.12
大阪市にある子ども園にて公開保育「おみせやさんごっこ」を見学し、各学年の製作過程等について発表する分科会、特別講演、造形実技研修に参加しました。日常ではなかなか経験することのできない他園の保育見学ですが、「おみせやさんごっこ」で、各クラスでおみせを展開しているのを見て、日々のあそびと生活によって得た、人とのやりとり、協力しあうこと、役割に責任をもつことが子どもたちの活動にいかされていることを感じ、刺激をうけました。また実技研修では、子どもたちと簡単に作ることのできるペーパークラフトを学びました。見学して学んだことを少しずつ、自園でも還元できるようにしていきたいです。
【磯﨑 他1名参加 大阪市 認定子ども園】
- 10月30日 発達支援・障害支援者対象研修会
-
2018.11.01
『”児童虐待”について考える』
この研修では児童虐待についての理解や、対応等をたくさんの事例を通して学びました。虐待の判断は難しいことや、虐待がその子どもの人格形成に大きく影響することも教えていただきました。これからも子どもの人権擁護に努め、常に子どもの立場で考えられるようにしていきたいです。
【大野 他1名参加 すこやかプラザ】
- 10月25日 平成30年度幼稚園新規採用教員研修第7回
-
2018.10.29
今回の研修では、児童虐待についてと、食物アレルギーについて学びました。児童虐待についてはこれまでに何度も学んできましたが、改めて学ぶ事ができました。保育者は子どもたちにとって毎日関わる一番身近な大人であるので、子どもたちに寄り添えるような保育を目指していきたいなと思います。
食物アレルギーについては、園にもアレルギーを持っている子どもたちも来てくれており、また、園で出している給食や、預かり保育のおやつの提供など、日頃から気をつけていかなければいけないなと改めて感じました。
【大阪府教育センター 三木他5名】
- 平成30年度 幼稚園・認定こども園 新規採用教員研修会 秋季全体研修会
-
2018.10.22
体験発表として、二年目の先生からアドバイスを頂きました。誰にでも一年目はあり、失敗することもあると話していただき、安心に繋がりました。また、大方氏の講演では「子どもたちの気付き」について改めて考えることができました。子どもの様々な気付きを保育者も共感しなければならないと思いました。
最後にグループディスカッションでは、同じような悩みをもった先生方とお話しすることができ、とても良い機会になりました。これからも日々の保育の中で子どもたちの気付きに私たちも気付き、共感していきたいと思います。
【野村 他5人】
- 平成30年度 就学前人権教育研究協議会B(実技的演習)
-
2018.10.15
『つなぐ・つながる音楽遊び-音・言葉・動きを使ってコミュニケーションを楽しもう-』
今回の研修では実際にコミュニケーションを楽しむ音楽遊びを体験しながら、日々の保育で活かせるリズム遊びを学びました。コミュニケーションを取るのが苦手な子でも楽しめるようなグループゲームや少しの隙間時間に楽しめるリズムゲームなど、様々な遊びを知ることが出来たので、実際に保育に活かしていきたいと思います。
【佐藤 他2名 大阪府教育センター(大ホール)】
『気持ちを言葉に-自分の感情に気付き、伝え合う力の育成をめざして-』
他人の気持ちを知ること、自分の気持ちを話すことの難しさと幼児期から伝え合う力を伸ばすことの大切さを学びました。気持ちについて様々な表情が描かれたカードを用いてグループワークを行い、同じイラストでも人それぞれ違う捉え方があることについても学びました。今後も子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添う保育を行っていきます。
【寺口 他2人 大阪府教育センター(視聴覚研究室)】
- 8月18日 メイト サマースクール分科会④
-
2018.09.16
「野歩さんの‘遊び歌’はおまかせ!」
体を全部使って遊ぶあそびを多く学び、子どもたちにとっての歌あそび、表現あそびとは何かを考える研修でした。ただリズムにそって、体を動かすだけでなく自然と体が動く、こんな動きはどうかなと自発的に動くことこそ、本当の表現だと学ぶ事が出来ました。子どもたちと、リズムって楽しいと自然と踊りたくなるような遊びを楽しみたいです。
【平野 ホテルニューオオタニ大阪】
- 8月18日 メイト サマースクール2018 大阪大会
-
2018.09.16
「低年齢児から子育て支援まで造形遊びアイデアと活動のコツ」
今回の研修ではたくさんの造形遊びを行いました。とても楽しい活動だったので、保育にも活かしたいと思います。又、造形活動は完成した物を見るだけではなくそれまでの過程がとても大切であることを改めて感じたので、子どもたち一人ひとりの姿をしっかりと伝えていけるようにしたいです。
【高井 他4名参加 ホテルニューオオタニ大阪】
「新沢としひこの「ぼくのあそびうた」」
今回の研修では、歌うことや体を動かすことの楽しさを実際に体験しました。子どもたちに遊びを紹介する前に、まず保育者自身が遊び、楽しむことが大切だと改めて感じました。今後、保育をする中で、子どもたちが遊びたいと思ったり、楽しいと感じたりできるよう、保育者が見本となって遊びを楽しみたいと思います。
【松岡 他5名参加 ホテルニューオオタニ大阪】
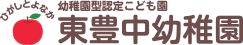

【谷本 他5名参加 豊中人権まちづくりセンター】