先生たちのポートフォリオ
- 8月17日 メイト サマースクール2018 大阪大会
-
2018.09.16
- 8月17日メイト サマースクール2018 大阪大会
-
2018.09.16
「絵本がつなぐよ、心の絆」
今回は様々な絵本を紹介していただきました。また、実際に読み聞かせのポイントも教えていただきました。様々な絵本がありますが、子どもたちと楽しむ前に、どういったテーマの本なのか、子どもたちの姿に適したものかをしっかり考え、その絵本の世界を、子どもたちと楽しんでいこうと思います。
【高橋他5名参加 ホテルニューオータニ大阪】
「表現する喜びいっぱいの発表会~オペレッタは成長の宝箱~」
今回の講義では、オペレッタについて学びました。なぜ、オペレッタが子どもの育ちに良いかというと、一つの作品を通して、教育要領の五領域を満たす子どもの成長発達の活動ができるからです。日々の保育にも取り入れて、子どもたちと楽しんでいきたいと思います。
【馬渕他5名参加 ホテルニューオータニ大阪】
- 8月8日教員のための博物館の日2018
-
2018.09.16
学校園の博物館利用を進めるために教員自らが博物館を楽しみ、学習や遠足の資料としての博物館を知る1日として学芸員の解説を聞いて見学したり、体験プログラムに参加したりしてより深く知ることができました。植物園、科学館、動物園の学芸員の説明に触れ、子どもたちが「なぜ?」「どうしてこうなるのか」と考えるポイントが各施設にはあることも改めて知りました。関西にはまだまだ博物館がありますので、多く足を運んで学びのポイントを還元できるよう研究していきたいと思います。
【磯崎 大阪市立自然史博物館】
- 8月7日 田研セミナー
-
2018.09.16
「遊戯療法の理論と実践-遊びが心を育てる-」
子どもが抱えている課題を、遊びの中で少しずつ解消できるという遊戯療法について学びました。また子どもが抱える課題によって取り入れるべき遊びが変わることも教わりました。子どもが今、どんな課題を抱えているのかを見極め、必要な遊びや遊具が選択できるよう今後も子どもたちの様子をよく観察し、遊ぶことを大切にしたいと思います。
【松山他1名参加 TWIN21 MIDタワー】
「保護者との面接のコツ」
この研修では、面接場面で必要とする姿勢や態度、マッピング法を取り入れた、クライエント(子ども・保護者)理解の方法を学びました。まずは、相手の思いを受け入れること、否定しないことが大切であると感じました。また、マッピング法では、相手が相手自身のことを「どう思っているか」「どう思いたいのか」を考えることができたり、共感する言葉を見つけることができたりと、相手の背景まで考えを深めることができました。この方法を多くの場面で取り入れ、子どもや保護者理解を深めていきたいです。
【大野他1名参加 TWIN21 MIDタワー】
- 8月6日、7日 新規採用教員研修会
-
2018.09.16
幼児期という大切な時期に、先生の存在が改めて大切だということが分かりました。先生の言葉掛け一つで子どもの成長に大きく関わるので、子どものことをしっかりと理解し、言葉掛けできたらと思いました。子どもたちを受け止め、一人一人に合った言葉掛けを心がけたいです。
【森 他5名】
今回の研修では、理論に基づく保育の重要性と環境を通じて、子どもたちの主体性を育むために必要な環境構成の技術や配慮を学びました。日々の保育の中で、「なぜ今この保育を行う必要があるのか」という問いに対して、子どもの姿や育ちを的確に捉え、根拠のある保育を行い、答えられるよう努めることが必要であると学びました。また、子どもが主体的に遊ぶ環境構成として、特に物的環境の観点から学ぶことが出来ました。子どもが遊びにのめり込め、子どもの思いを引きだせるためには、どの様な教材がいくつ必要なのかを子どもの育ちに合わせて読み取る力が必要であると実感しました。
【山本 他5名】
今回グループ内での助言者としてディスカッションに参加させていただきました。新任の先生方とお話する中で、自分自身も先生方から学ぶこと、気付かされることがあり、いい刺激を受けました。また、様々な園の先生方と意見交換することも新鮮で、貴重な経験となりました。
【上田 計1名】
- 8月6日 田研セミナー
-
2018.09.15
「幼児心理カウンセリングの基本~その理論と方法~」
カウンセリングがどのように世の中に広まっていき、カウンセリングとは何なのかを学びました。また実施するに当たって気をつけることが多くあることも、学ぶことが出来ました。カウンセリングを受けることで、他人に自分の悩みを共感してもらったり、分析してもらったりし、少しでも心が晴れるのだと思うと、とても大切な事なのだと感じました。カウンセリングまではいかなくとも、他人の心に寄り添える人、この人に話を聞いてほしいと思ってもらえるような人に、なっていきたいです。
【篠原 他2名】
「社会情動的スキルと幼児教育の実践」
この研修では、社会情動的スキルを育む重要性や、これからの社会で生きる教育のあり方等について学びました。社会情動的スキルとは、学びに向かう力や人間性であり、それらを育むには、幼児期における質の高い保育が重要であることを学びました。中でも振り返りの中で、人間関係を教えることが大切であることも教えていただいたので、これからの保育でも、振り返りの時間を大切に、有意義なものにしてきたいです。
【大野 他2名 TWIN21 MIDタワー】
「子どもたちの‘今‘を育み‘未来‘につなぐ」
子どもの成長を見守るには、まず一人一人の個性を理解し寄り添い信頼関係を結ぶことが大切だということを再確認することができました。子どもが求めていること、その子どもの長所や苦手な分野を知ることが支援の第一歩だということを学びました。一人一人の成長にあった援助ができるよう、また保護者に子どもの様子をしっかり伝えられるように保育していきたいです。
【松山 他2名】
- 8月5日田研セミナー
-
2018.09.14
「子どもも親も保育者も輝いて育ち合う保育」
今回の研修を通じて「子どもの個性」を尊重することに対して、あらゆる面から学ぶことができました。子ども1人ひとりのあらゆる個性を、温かいまなざしで見守り、受容的、応答的に関わり、その子どもの個性を伸ばすことで、子どもたちの可能性が広がります。子どもを取り巻く大人が、「気づきのアンテナ」を鋭くすることで、子どもの長所は更に伸び、苦手に感じている部分も強みに変わっていきます。子どもの可能性を制限してしまうような言葉や見方を避けて、子どもがのびやかに過ごせるよう見守り受け止めることが大切だと学びました。
【山本他5名参加 TWIN21,MIDタワー】
「たくましい心と体を育む運動指導-子どもと一緒に創る運動遊び-」
今回の研修では、運動意欲を高めるためにすることは教えることではなく、教えなくても子どもたちは自由な遊びの中から自然と学んでいるということを教えていただきました。子どもの自己決定(遊び要素)の多い運動ほど運動能力が高くなるというところで、大人が介入するほど遊び要素が少ないため、いかに子どもたちだけで主体的に遊ぶことができるよう関わっていかなければいけないと思いました。また、遊ぶ楽しさを知る、遊びの場を一緒に創ることの大切さを学ぶことができ、これからの保育でも取り入れていきたいと思います。
【藤田 他5名】
「主体的に生きる子どもを育てる -子どもをまんなかに-」
保育という営みは「子ども理解」から始まるということを重きにおき、保育者が日々の保育の中で、子どもたちとどのように関わっていくべきなのか、子どもたちの育ちをどのように理解していくべきなのかということを学びました。日常の中での子どもたちの気付きや、小さな変化一人一人の成長を一緒に楽しみ、喜びながら、今後も保育に取り組んでいきたいです。
【宝珠山 他5名】
- 8月5日、6日赤十字幼児安全法講習会
-
2018.09.14
幼児に起こりやすい事故とその予防、また応急処置のしかたについて学びました。
応急処置については、人工呼吸と心臓マッサージ、AEDの使い方を実習で体験しました。これは、これまでにも何度か消防の方から教えていただいた事柄ですが、何度も何度も学ぶことによってしっかりと身に付けることができると思うので、再度学べて良かったと思いました。これからも子どもの命を守るために、こういった研修を積極的に受講していきたいと思います。
【天野 赤十字兵庫支部】
- 8月3日第67回幼児教育大講習会
-
2018.09.13
「幼児教育とは~新要領・指針のポイントとこれから~」
この研修では、新要領・指針のポイントを押さえながら、”幼児教育”について学びを深めました。様々な年齢や場面で見られた子どもたちの様子をビデオでいくつか拝見させていただきましたが、改めて子どもたちの持つ力に感心させられました。この子どもたちの力を伸ばしたり、引き出したりすることも保育者の役目だと思います。活動や遊びの中で見られる子どもの姿をよく捉え、援助も日々試行錯誤しながら柔軟に対応できるよう努めていきたいです。
【上田他10名参加 大阪市中央公会堂】
「マジック・音楽・絵本~こどもの世界を彩る3つの魔法~」
この研修ではマジックやけんばんハーモニカ、ピアノ、絵本などで保育を楽しくする方法を学びました。マジックをしているところや、けんばんハーモニカを指1本ではなく2本で弾くと、3本で弾くと...などと色々なことを見ているだけで楽しくなりどうしてそうなるの、どんな音になるのかなとワクワクしました。今回学んだことを保育に取り入れ子どもたちのドキドキ・ワクワクした表情が見られるようにしていきたいと思いました。
【藤田他10名参加 大阪市中央公会堂】
「ポジティブのすすめ~前向きな心は、保育や子どもを楽しく明るく変えていく~」
今回の研修で、言葉がもたらす力の大きさを感じました。言葉を伝えるには、自分の心の状態がとても大切であり、自分自身の心を整えてから言葉を選択すると、相手により伝わりやすくなることを学びました。一つひとつ丁寧な言葉を選び、子どもたちと関わっていきたいと思います。
【金他10名参加 大阪市中央公会堂】
- 8月2日平成30年度幼稚園新規採用教員研修
-
2018.09.13
今回の研修は人権について改めて学び、博物館見学にて、実際に資料を見て学ぶことができました。人権は子どもから大人まで、誰にでもあるものであり、自分の意思を伝えることはとても大切な事です。子どもたちの中には、まだ自分の思いをなかなかうまく伝えることが難しい子どももいるかと思います。そんな時、私たち保育者は、子どもが伝えやすいように気持ちを表現したイラストを使ってみるなど、工夫をしながら子どもたちの気持ちに寄り添う事を心掛けたいと思います。
【三木他5名参加 大阪人権博物館】
- 7月30日平成30年度幼稚園新規採用教員研修 第5回
-
2018.09.13
「これまでの実践を振り返る」「リズム運動」
今回の研修では、今までの研修を振り返ると共にレゴを使って1学期を振り返りました。新任の先生方とそれぞれの1学期の出来事を共有し、また、レゴを使って印象的な場面を作り楽しみながら1学期を振り返る良い機会となりました。
リズム運動では、実際にダンスを踊り音楽に合わせて体を動かすことの楽しさを味わったり、発表会や運動会などにも役立てられるような振り付けのコツを教えていただきました。今回学んだことを活かして指導する際は工夫していきたいと思います。
【野村 他6名参加 大阪府教育センター】
- 7月28日29日 第33回食と健康を考えるシンポジウム
-
2018.09.13
「こだわる、食べられない、食品幅が広げられない、そんな子どもの気持ちに寄りそうための心理学」
園生活の中で給食は食育や食べる楽しさなど、子どもたちの中に育てたいことがいぱいありますが、しかし中には苦手な子どももいるのでしっかりと一人ひとりの気持ちに寄り添うことが必要だと改めて感じました。
食事1つでも子どもの不安や家庭環境が分かるということが分かったのでそのようなところにも着目したいきたいと思いました。
【寄吉 天満研修センター】
「じょうずにかんで、しっかりゴックン」
離乳食の過程について学ぶことができました。乳児期は赤ちゃんの口腔機能の発達に適した調理方法や食材を選び、”食べることが楽しい”と感じられるようにすることが大切だと改めて感じました。また、口を動かすことがその後の発語にも関わるということを知りました。食べることは、生きる力につながるということなので、楽しく食事をとれるように促していきたいと思います。
【寄吉 他1名参加 天満研修センター】
- 7月23日 平成30年度幼稚園新規採用教員研修 第4回
-
2018.07.26
「保護者理解と家庭との連携のために―カウンセリングの理論と実際-」
今回の研修では、幼児期の子どもの発達とこころの成長を願うためには専門知識だけでなく保護者の気持ちに寄り添い、同じ到着目標を目指すことを軸として関係づくりをすることを学びました。そのためには、明確化、感情に焦点を当てる、聴いた内容の確認、解釈と確認の4点を通してコミュニケーションをとることが大切であることがわかりました。
これからの保護者との連携において、一人ひとりの方と丁寧にかかわり子育ての不安が少しでも軽減できるよう、気持ちに寄り添いながら関わりをもちたいと思います。
[ 寺口 他5名参加 大阪教育センター 大ホール ]
- 7月17日 豊中市発達支援・障害児支援者対象研究会
-
2018.07.20
『発達に課題や障害のある子どもへの支援Ⅰ』
気になる子どもの感じ方、気持ちを想像する大切さを学びました。集団活動を苦手とする子どもに、安心することができる居場所を作ってあげ、その居場所を正当化してあげることを教えていただきました。これからも子ども一人ひとりにあった援助ができるよう保育を行っていきたいと思います。
【金 他3名 すこやかプラザ】
- 7月5日 平成30年度 幼稚園新規採用教員研修 第3回
-
2018.07.12
『セルフマネジメント-メンタルマネジメント-』『指導案・指導計画の作成』
「セルフマネジメント-メンタルマネジメント-」の講義では、体調だけでなく、心の健康を保つことの意義を学ぶことができました。「私」を主語にして自分の気持ちを伝えるということはとても難しいですが、それを全員が実行できれば、ストレスを感じる人は減るのではないかと感じました。「指導案・指導計画の作成」の講義では、「1日の見通しがもてる」「ねらい・内容がはっきりする」「活動のイメージがわく」「振り返り・今後の参考」「子どもの気持ちを客観視できる」といった指導案作成のポイントについて学び、これらのことの重要性をあらためて感じました。今回学んだことを活かして日々の保育に励みたいと思います。
【佐藤 他5名 大阪府教育センター】
- 7月3日 就学前人権教育研究協議会A
-
2018.07.05
『人権尊重の観点に立った就学前教育の今日的課題の解決に向けて』
今回は障がい者の方の人権問題や児童虐待の問題、男女平等の問題等、今日課題とされている人権問題を幅広く学ぶことができました。中でも、児童虐待について深く学びました。虐待が発生してしまう背景として、「子どもの貧困」と「子育ての孤立化」が挙げられ、それらが負の連鎖として続いてしまう悲劇もあります。子育てに悩みを抱えている家庭内で、経済的に困窮している方々が孤立してしまわないよう教育機関のみならず自治会やNPO法人など、地域で包括的に子育て世帯をサポートしていくことが大切だと実感しました。
【山本 他5名 大阪府教育センター】
- 6月30日 大阪府臨床心理士会主催第2回公開講座
-
2018.07.04
『ストレスに「折れない」心の持ち方、育て方~しなやかに自分らしく人生を味わうために~』
毎日生活していくうえで、さまざまなストレスが次々に降りかかります。過度なストレスは、心や体の不調になる現代ですが、心と体の健康を維持して起こりくる逆境に向かい合い、ストレスと上手に向き合う工夫をこの研修で教わりました。おかれている状況を分析し、自分にできる行動を考える、そして助けを得る、また助け合うことで、日々の生活が今より少し幸せになります。学んだことを職員で共有し還元できたらと思います。
【磯崎 大阪市中央公会堂】
- 6月28日 障害児保育研修
-
2018.07.04
『発達障害の子どもお特性とその対応~感覚特性から考える~』
今回の研修では、発達障害の子どもの脳機能の発達や感覚特性をふまえた、支援や取り組みについて学びました。まずは子どもの「得手・不得手」を明確に理解した上で、褒めたり、認めたりといった心の援助をしていく大切さを教えていただきました。子どもたちが幼稚園で安心して過ごせるような環境作りや一人ひとりに合った援助ができるよう努めていきます。
【松岡 他1人参加 豊中まちづくりセンター】
- 6月16日 豊私幼A研修
-
2018.06.26
「こどもと楽しむ絵本の世界」
絵本にはさまざまなメッセージがあり、それは、表紙、中扉から始まっています。物語は絵本全体に含まれており、表紙からしっかり子どもの心を引き付けることが大切だと思いました。絵本を通して、子どもたちが成長できるような読み聞かせを心がけたいと思います。
【森 他10名 豊中市立文化芸術センター】
- 6月16日 豊私幼B研修
-
2018.06.26
今回の研修では、発達障がいの子どもの特性や関わり方について学びました。障がいの有無に関わらず、幼児期は個人差が大きいので、今後も一人ひとりの成長や個性に合わせた保育を行っていきたいと思います。
【寄吉 他7名 豊中市立文化芸術センター】
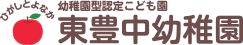

今回の研修では、実際に体を動かして、たくさんの体操や運動遊びを行いました。どれもとても楽しい活動で自然と笑顔で様々な人と関わりながら取り組むことができました。幼稚園でも子どもたちと一緒に楽しみたいと思います。
【高井 他5名参加 ホテルニューオータニ大阪】
「ロケットくれよんのジョイ!ジョイ!ジョイ!~広がれ!みんなの喜びの輪~」
今回の研修では、講師の方々が実際に子どもたちと触れ合った経験からつくるあそび歌やパネルシアター等をたくさん教えていただきました。
あそび歌は、2人組のペアになって楽しむものもあれば、集団で楽しむものもあったりと様々で、リズムに合わせて友だちとの触れ合いを楽しんだり、少し考えながら遊んだりと子どもも大人も楽しめるものばかりでした。また、実際に体験することで、あそび歌の楽しさや面白さを感じることができ、講師の方々の姿から保育者がなによりも楽しむことが大切だと思いました。今回体験したあそび歌を保育の中に取り入れ、子どもたちと楽しい時間を共有して元気な声と笑顔あふれる保育を作っていきたいと思います。
【椹 他5名参加 ホテルニューオータニ大阪】