先生たちのポートフォリオ
- 8月4日 ひかりのくに 第64回幼児教育大講習会 第2日目
-
2015.08.31
- 8月4日 ひかりのくに 第64回幼児教育大講習会 第2日目
-
2015.08.31
「運動会はこれでバッチリ!!」 実技講習
講師の方が考えられた子どもが楽しめるような体操を、私たちも実際に教えて
いただき、体を動かしました。それらの体操は、童謡をアレンジしたものや、オリジナルのものから、たくさんの音楽に合わせて体を動かすことでとても楽しく取り組むことができ
ました。
講師の方々の笑顔で楽しく話されている姿を見て、こちらも楽しく取り組めたのだと
思うので、私たちも日々の保育で一緒に楽しみながら何事にも取り組んでいきたい
です。また、教えていただいたことも子どもたちと楽しめたらなと思います。
【目黒 絵梨奈 他6名参加 大阪府立中央体育館】
- 8月3日 ひかりのくに 第64回幼児教育大講習会 第1日目
-
2015.08.31
「保育の質を考える ~真に質の高い保育とは~」
幼児期に大切にされたこと、されなかったことは大人が思っている以上に子どもの
人生に影響を与えているのではないか?ということや、子どもたち一人ひとりに
愛おしさを持ち、肯定的に捉えながら大切に関わることがいかに大事なことなのかと
いうことを多くのエピソードを交えながら教えていただきました。
これからも子どもたち一人ひとりを大切に、保育者も日々向上心を忘れず、力を
合わせながら保育をしていきた思います。
【瀬戸口 優子 他1名参加 大阪市中央公会堂】
- 8月3日 ひかりのくに 第64回幼児教育大講習会 第1日目
-
2015.08.31
「いつも心に歌を」 音楽・実技講演
講師の先生の歌声はとても綺麗で、心地よく歌をきくことができました。子どもたちと
一緒に歌いたい曲や手遊び等がいくつかありましたので、是非また園で取り入れたいと
思います。
【篠原 理恵 他1名参加 大阪市中央公会堂】
- 8月3日 ひかりのくに 第64回幼児教育大講習会 第1日目
-
2015.08.31
「願えば叶う ~きれいな自分を作り、よりよく生きるとは~
どのように生活をすれば、いつまでも美しくいられるかの話をきかせていただき
ました。毎日を規則正しく過ごすことや、大好きな事や人を多く見つけることが大切
だとおっしゃっていました。
先生は、顔とは①健康のカルテ ②心の証明 ③人生を物語っている
と、教えてくださいました。
「楽しい人生なんだな・・・」と他人に思ってもらえるような顔になれるように
日々、ポジティブに健康に過ごしたいと思います。
【篠原 理恵 他1名参加 大阪市中央公会堂】
- 8月3日 田研セミナー
-
2015.08.31
「ほんものの保育をしよう」
~自分にウソをつかないように~
この講演では、講師自身の保育経験を基にお話してくださり、大変勉強になること
ばかりでした。また、自分たち自身の保育についても振り返ることができました。
講師もおっしゃっていましたが、“保育の原点は子どもの喜びです。これからの
毎日も子どもの喜びを最優先に考え、子どもたち一人ひとりに寄り添うことのできる
保育者を目指していきたいです。
【上田 茅波 他5名 TWIN21 MIDタワー】
- 8月3日 田研セミナー
-
2015.08.31
「子どもの発達と生活リズム」
子どもの発達について学びました。時代の流れと共に、子どもの発達段階や生活の
流れが変わってきているということを詳しいデータと共にお話していただきました。
ユニークな話し方や、実話などを交えての講演だったのでとてもわかりやすく、面白く
聞くことができました。
幼稚園の子どもたちを見守っていくと共に、子どもたちの変化に気づいていけるように
努めたいと思います。
【西田 藍 他5名参加 TWIN21 MIDタワー】
- 8月3日 田研セミナー
-
2015.08.31
「子どもの心に目を向けてみませんか」
この講義では、子どもの心を育てる保育について考え、理解を深めることができ
ました。子どもたちは、大人の言葉や態度を敏感に感じているということを改めて
感じ、自分自身の保育を見つめ直すと共に、これからも子どもたち一人ひとりに寄り
添った関わりを大切にしていきたいです。大人主導の「させる」保育ではなく、子どもの
心に目を向ける保育の重要性を感じました。
【福田 葵 他5名参加 TWIN21 MIDタワー】
- 7月23日 近研・大阪大会 第3分科会
-
2015.08.13
「子どもの発達障害と幼稚園、そし保護者とのかかわりについて」
発達障害を持つ子どもと、支援している保育者の関わりや専門機関・小学校との
連携など、事例をもとにした障害について考える時間となりました。子どもがどういう
思いで言った言葉なのか、どういうことを考えてとった行動なのか、子どもの気持ちに
寄り添い、周りの大人が理解しを示して受けとること大切だと感じました。
今後も1人ひとりの子どもと向き合いながら、学びを深めていきたいと思います。
【牧田 茉里 他3名参加 グランキューブ大阪】
- 7月23日 近研・大阪大会 第2分科会
-
2015.08.13
「社会性の育ちについて
~保育者の友だちとのかかわりを通して~」
幼児期の子どもたちが集団生活の中で、どのようにして社会性を身につけていく
のか、他園の3歳児・4歳児・5歳児の事例の発表を拝聴しました。具体的な例で
共感できることも多く、子どもたちが人と信頼関係を築き、集団生活の中で主体的に
活動し、自立していこうとする社会性の育ちにはどのような関わりや援助が必要かと
学びました。
子どもたち1人1人の成長をしっかり見守りながら、自律性が育めるよう、保育していきたいと思います。
【藤本 真知子 他2名参加 グランキューブ大阪】
- 7月22日 近研・大阪大会 記念講演
-
2015.08.13
「夢は努力でかなえる」
トップアスリートでスキージャンプという競技を長年にわたって続けられ、
冬季五輪大会連続出場という輝かしい功績をお持ちの葛西さんの講演でした。
第一線で続けられているのは体力、精神力を高めるためにトレーニングを欠かさない
ことや、応援してくださる方すべてに感謝の気持ちを持ち続けておられるからだそう
です。
目標は高くありながらも、謙虚で優しく、人に接する姿勢に強さが生まれるのだと
話を聞いて実感しました。
「努力すると、いつか夢をかなえられる」という勇気をいただきました。
【磯﨑 加奈 他8名参加 グランキューブ大阪】
- 7月22日 近研・大阪大会 基調講演
-
2015.08.13
「新制度時代に」おいて、また、これからの社会において求められる教育のあり方に
ついて学びました。
社会や生活の変化に伴い、子どもたちの本来の姿である「生活の中で育つ」という
ことが難しくなっている今育ちにくくなっているそのような面をしっかりと意識し、保育して
いきたいと思いました。
【姫島 里佳 他8名参加 グランキューブ大阪】

- 7月11日 園内研修
-
2015.07.17
今回は、園の教育課程についての話し合いと職員の1学期の振り返りを
しました。教育課程の話し合いでは、各学年に分かれて1学期の子どもの姿を
振り返り、内容の見直しや、付け加えられる点を話し合いました。
また1学期の振り返りでは、個人、学年の反省点、今後に活かせる点を
職員間で共有しました。
これからも年齢、個性に合わせた保育ができるようにしていきたいです。
【 寄吉紗奈愛 全員参加】
- 6月20日 教育現場での熱中症対策セミナー
-
2015.06.22
熱中症事故の予防と事故が起きてしまった時の対策を
専門の研究者と医師の観点から聞かせていただきました。
職員全員が熱中症を正しく理解し、日常の保育に役立てて
いきたいと思います。
【井上啓子 他4名参加】 TKPガーデンシティ東梅田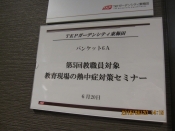
- 6月19日 平成27年度 就学前人権教育研究協議会A(全体会)
-
2015.06.22
「大阪府における人権教育推進の課題」
「親学習について」
「幼児教育における人間関係作り
~子どもの人権を大切にした保育について~」
子どもの人権を大切にする教育とは、「対等の関係」で、子ども同士が
関われることであると今回の研修で学びました。そして、子どもが自分の
思いや気持ちを出し合ってもよいと気づかせてあげたり、そのような雰囲気を
作っていくのが、私たち保育者の役割であるということを、さらに実感することが
できました。
【馬渕 美里 他2名参加 】 (大阪府教育センター)
- 6月12日 園内研修
-
2015.06.22
今回の研修は、ビッグブッグの教材研究を行いました。
ビッグブックとは、大型絵本とは違って子どもたちと一緒に物語を考えることが
できたり、楽しみながら文字に興味を持ったり、想像力を豊かにする教材の一つです。
実際にビッグブックの文字を隠しながら見て楽しみ、子どもにどのように読むのかを
全員で話し合いました。
これからもビッグブックのような様々な教材研究をし、子どもたちが楽しめることを
実践していきたいと思います。
【山取彩夏 全員参加】

- 6月10日 平成27年度幼稚園新規採用教員研修(第2回)
-
2015.06.12
「子ども理解・保護者理解」「障がいのある子どもの理解と支援
今回の研修では、「子ども理解」について学びました。
園生活の中で子どもたちが自分で自分を認められるように保育者は
周りの環境を整えることがとても重要なことだと改めて認識することが
できました。
「気づき」が「支援」の始まりであり、子ども一人ひとりをしっかりと見て、
一人ひとりの「特性」について保育者同士が共通理解を図り、根拠のある
支援を実践的に行っていくことで子どもを尊重していけると感じました。
そのためには、事前準備などの工夫が大切であり、この工夫が子どもたちの
活動の支援にもつながると思います。
適切な支援ができるようにもっと知識を身に付けていきたいです。
【櫻井 友美 大阪府教育センター】
- 5月27日 ぐりとぐら展に行ってきました。
-
2015.05.28
おとなからこどもまで世代を超えて親しまれている「ぐりとぐら」は、
今年で50周年を迎えました。会場では、ぐりとぐらのお話全7作品の
貴重な原画や、「そらいろのたね」「たからさがし」の原画も展示されて
いました。
絵本の創作の原点に触れ、読書コーナーで作品を閲覧することもでき、
あらためてぐりとぐらのぬくもりあふれる世界を感じることができました。
【磯﨑加奈 他2名参加】 (伊丹市立美術館)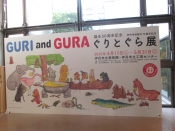
- 5月23日 園内研修
-
2015.05.27
今回、私たちは6月から子どもたちと遊ぶ水つなぎの教材研究を
行いました。
水つなぎとは、透明カップの底や側面に様々な穴をあけ、そのカップに
色水を入れ遊びます。子どもたちが水の流れる不思議さやカップをつなぎ、
流れをつなげる楽しさを味わえるよう、職員全員でどのように遊びの導入を
するかを話し合いました。
これから子どもたちと共に遊び、より考えて遊びを深められるよう教材研究にも
力を入れていきたいです。
【平野 愛 全員参加】

- 5月9日 豊私幼研修 全体会
-
2015.05.11
人が育つには、人・物・事との関わりが大切と教わりました。安心、安定した
人間関係の中で「これをやってみたい」「楽しい!!」と思えるような保育の
環境づくりを日々研究し、職員同士で情報共有や意見交換を重ねて
いきたいと思いました。
子どもたちが五感を使ってワクワク・ドキドキするような豊かな体験が
できるような保育づくりを、職員が一丸となって行い、日々の保育を振り返り
明日への実りとなるように研究していきたいと思いました。
【磯﨑 加奈 全員参加】 (豊中市アクア文化ホール)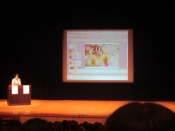
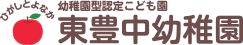

お遊戯を考える時や教える時に、「伝える」という手段を簡単に説明できる
「オノマトペ」を学びました。「オノマトペ」はキラキラ・クルクルなど、音のリズムに
合わせて身体を動かすと覚えやすかったり、子どもたちと音のリズムに合った振りつけ
を考えたり、簡単にできると知りました。
実際に身体を動かし体験させていただき、リズムに合わせて身体を動かす楽しさを
実感しました。子どもにわかりやすく、楽しいステップや手の動きが指導できるか、
声かけのポイントも学ぶことができたので保育の中に取り入れ、子どもたちにリズム
に合わせて身体を動かす楽しさを伝えていきたいです
【櫻井 友美 他6名参加 大阪府立中央体育館】