先生たちのポートフォリオ
- 6月13日 園内研修
-
2014.06.18


- 6月15日 大阪医科大学LDセンター研修
-
2014.06.17
「幼児期の発達障害のある子どもの理解と支援
~保育園・幼稚園の行事を含めた集団生活での対応~」
今回は上記の内容で講演を聞かせていただきました。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)や自閉症スペクトラム(自閉症・アスペルガー症候群・高機能自閉症)を抱える子どもの特徴についてお話を聞きました。
例えば、遠足では新しい環境が苦手でパニックを起こしてしまったり、運動会では集団行動からはみ出してしまったり、勝手な行動をとってしまうなど、様々な子どもがいます。一番困っているのは、子ども本人です。保育者が対象児の特性を把握し、どの様な場で困り易いか予測し、具体的な対応策を考えておくこと、その子どもが参加しやすくなるよう支援技術を向上させていくことが大切だと感じることが出来ました。
【大麻 舞 6名参加】 (大阪医科大学)
- 6月14日 大阪医科大学LDセンター研修
-
2014.06.17
「幼児期の身体を使った遊びが感覚や運動の力を育て学習する力につながる
~不器用、多動のある子どもが楽しんで参加できる遊びとその意味~」
今回、子どもたちの成長に関わる感覚の育ちについてまず学びました。
多動や不器用な子どもたち、または自閉傾向にある子どもたちの特徴を知り、姿勢保持に必要な体幹を育てる遊びを具体的に教えていただきました。
体幹を鍛えることは、どの子どもたちにも共通すると思うので、園内でも遊びを提供し、運動する力・姿勢保持する力を育て、集中力や考える力が育つよう援助して行きたいです。
【平野 愛】(大阪医科大学)
- 5月24日 豊中市私立幼稚園連合会研修会 全体会
-
2014.05.27
「子どもを人間として見る」ということ
今回の研修では、前成説モデルについて学ぶ事が出来ました。
子どもは、生まれた時から一人ひとりが自分で自分を育てよう、と考える力、意欲を持っているので、保育者はその気持ちを感じとり、援助していくことが大切であるという事を学び、日々の自分たちの保育を見直していきたいと思いました。
また、子どもの願いを「きく」「応答する」誘導保育を、いくつかの例を見て学ぶ事が出来ました。
【山取彩夏 6名参加】(千里ライフサイエンスセンター)

- 5月20日 大私幼子育て相談員認定講座①
-
2014.05.21
子育て相談のシステムⅠ
~子育ての現代的理解と子育て相談のシステム~
年間10回の講座の中で、専門性を高められるよう学んでいきたいと思います。
子どもにとって、とても大切な“愛着”。 愛着とはイギリスの医学者J.BOWLBY
の言葉で、「子どもが不安を感じたり、危機的だと感じる状況で、特定の養育者との間で情緒的な安定を取り戻そうとする行為」とあるように、身近な養育者が子どもにとって、安心、、安全の基地であることの大切さを唱えています。
愛着不全は、愛着障害や人格障害に至る危険性があると言われる中、私自身も子どもとの関わり方を見つめ直し、子どもには充分あまえさせてあげたいと思いました。
家庭が「まじめ信仰」「きっちり地獄」「べきねば症候群」になっていないか、子どもにより高い能力を期待しすぎていないか。
親(自分)の考えが正しい(一番)という気持ちが強くなっていないか、情報が溢れる今日の中で、取捨選択ができず、振りまわされていないか等、時には振り返りながら子どもに愛情を注いでいきたいです。
【井上啓子】 (私学会館)

- 5月18日 日本保育学会第67会大会 発表
-
2014.05.21
「幼児の自律性と協同性を育てる保育実践(2)」
-5歳児クラスでの小グループによる活動を通してー
発表者・・・篠原・平野・髙井・髙橋

- 5月18日 日本保育学会第67会大会 発表
-
2014.05.21
「幼児の自律性と共同性を育てる保育実践(1)」
-3年間の育ちの連続性に着目してー
発表者・・・右松・氏林・中村・牧田

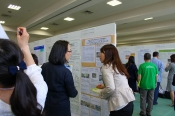
- 5月18日 日本保育学会第67会大会 聴講
-
2014.05.21
保育環境評価スケール」と保育者の資質向上
-保育環境撮影と手引きの作成ー
保育の質を項目に沿って7段階評価の数値で表す保育環境評価スケールを用いて、保育環境について研究されていた先生方の実践発表を拝聴させていただきました。
各コーナー遊びの机、椅子の置き方、また仕切りを作るなどの工夫で子どもの遊び方に変化があること、そして子どもたちの遊びがより広がるような玩具を用意することの大切さを学びました。
子どもたちがより遊びこめるように、自身の保育環境を見つめ直していきたいと思います。
【田之上真知子 全員参加 (この分科会2名)】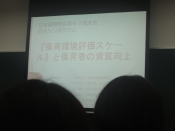
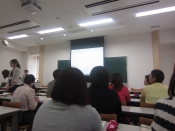
- 5月17日 日本保育学会第67回大会 聴講
-
2014.05.21
「保育者の資質能力 保育者の専門職性」
保育の質を高める自立的な園内研修を実施していくためには、自分の保育を振り返ることの大切さ、そのためにエピソード記録、メディア(映像や写真)での記録をすることの有効性、そして職員同士が意見を言いやすい雰囲気作りが重要だという事を学びました。
園全体の保育の質の向上を目指して、今後も保育に行かせる園内研修を重ねていきたいです。
【松山絢子 全員参加(この分科会は2名参加)】
- 5月14日 第1回公私立幼稚園教員研修
-
2014.05.16
「こころを育む絵本の力」
子どもたちにとって、絵本とは読んでもらうものであり、大好きな大人に絵本を読んでもらう体験(経験)こそが、子どもの心の安定につながり、想像力や聞く力を育む機会になることを学びました。
また、様々な絵本を紹介していただきながら、よい絵本とはどのようなものか知ることが出来ました。
今後、この研修で学んだことを活かして、子どもと絵本を読む時間を大切にしていきたいと思います。
【目黒絵梨奈 4名参加】 (豊中人権まちづくりセンター)
- 5月11日 カミイ博士セミナー
-
2014.05.14
子どもはどのように数を構成するのか
-幼児期から児童期への発達と教育ー
今回、ピアジェの「構成論」に基づく幼児教育を確立した教育学者として活躍されておられるカミイ博士のセミナーに参加しました。
研修に参加し、子どもたちがどの様に数を身につけていっているのか、また数を習得するためには何が大切であるのかという事を学びました。
ただ”1・2・3・4・・・・・”という言葉として数を覚えるのではなく、子どもたちが自分の頭の中で考えて答えを導き出さなければ習得できません。そのため、計算式を解くよりも文章問題から始めるほうが自分で考えることが出来、望ましいと教えていただきました。
これからも、子どもたちの自分で考える力が育つような保育をしていきたいです。
【髙井千尋 全員参加】 (甲子園二葉幼稚園)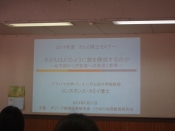
- 4月30日 平成26年度幼稚園新規採用教員研修
-
2014.05.02
「大阪府の幼稚園教育」「幼稚園教育要領と幼児理解」「先輩教員の実践に学ぶ」
大阪府の公立・私立の新任先生方が集まる研修会に参加させていただきました。
教育センターの方や現場の先生方のお話しを聴講させてもらい、これからの園での子どもとの関わり、また先生としてだけでなく社会人としての在り方についても学ばさせていただきました。
この新任研修は、一年間通して行われるため、気持ちを引き締めて参加し、学ばせてもらおうと思っています。
【増田遼介 4名参加】 (大阪府教育センター)

- 4月26日 大阪医科大学LDセンター研修会
-
2014.04.30
「発達に偏りや遅れのある子どもを持つ保護者への支援」
~保護者の気持ちに寄り添いながら子どもを支援するには~
今回、上記のテーマで講演を聞かせていただきました。
周りにいる物として、何が出来るのかというところで、保護者のあゆみを理解すること、親の思いに共感し保護者としての地力(底力)を付けてもらえるようにする。そして、発達と障害についての正しい理解を知ることがとても大切だと教えていただきました。
これからも子どもがよりよく成長するために、保護者に寄り添い連携しながら子どもの成長をともに喜んでいきたいと思いました。
- 4月19日 園内研修
-
2014.04.29
今回は「構成論」について、職員全員で理解を深めました。
構成論とは、「子どもたちは大人に教えられて覚えることが知識に繋がるのではなく、自ら考え、答えを見出す経験が知識に繋がる」というピアジェが提唱した理論です。
日々の子どもたちの姿を思い浮かべ、子どもたちが育つためのより良い方法を考え、話し合いました。
今回の研修で学んだことを活かし、子どもたちとの関わりの一つ一つを大切に保育していきたいと思います。
【石原楓子 全員参加】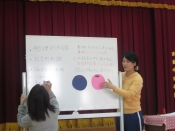

- 4月5日 園内研修
-
2014.04.09
東豊中幼稚園の教育理念や子どもの“自律性”を育むための保育者のあり方について様々な事例を基に、皆で意見を深め合いました。
東豊中幼稚園が目指す保育について全職員で共有することが出来た学びのある有意義な研修でした。
4月から自分自身が目指す保育者像をしっかりイメージし、子どもたちはいったい何をかんがえているのかと、常に子ども目線で考え、遊び心を持ちながら関わり、遊びを発展、充実できるように保育していきたいです。
【谷本 里佳 全員】


- 3月28日 合同研修 (やまなみ幼稚園と) 午後の部
-
2014.04.09
養成校付属幼稚園園長先生のお話しを聞かせていただきました。
自園について写真とエピソードを交えながらお話しをされ、子どもたちとの関わり方、援助について学びました。
子どもの好奇心を育てる事が学びに繋がるという事で、これからやってみたいという意欲を大切に、4月からも一人ひとりの成長を大切に保育していきたいです。
【中村 すみれ 全員参加】 (ドーンセンター)
- 3月28日 合同研修 (やまなみ幼稚園と) 午前の部
-
2014.04.09
マナー研修
新年度の始まりに、社会人としてのマナー・好感をもたれる話し方という、とても大切な基礎を学びました。
子どもたちや保護者と常に関わりを持つ私たちは、日頃から笑顔やあいさつを心がけ、周りの人へも心地よい環境を与えていきたいです。
【平野 愛 全員参加】 (ドーンセンター)
- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 第5分科会
-
2014.04.09
特別支援教育「発達障害児の行動面や対人関係面への指導・支援」
今回、様々な発達障害児の特徴や注意する点、また指導・支援についてや講師が実践されている遊びや援助について教えていただきました。
お話の中で、子どもの目に見える姿を捉えるだけでなく、それよりももっと深い「どうしてその行動をしたのか」という姿を見て、その子どもの気持ちに寄り添う事、叱るだけでなく誉める事の大切さを感じました。
また、性格や個性が一人ひとり違うように、同じ障害を持っていても症状の特徴が違うため、私たちは障害の名前に囚われ過ぎず、子ども一人ひとりと向き合い理解しようとする姿勢を持つ続けなくてはならないと思いました。
そして障害を持つ子どもが日々楽しく生活を送ることが出来るよう、今後も知識を深めていきたいです。
【髙橋 ちさと 4名】
- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 第4分科会
-
2014.04.09
「コミュニケーション・スキルアップ」
今回の研修では、コーチングとは①双方向性 ②継続性 ③個別対応 の3原則を持ち、相手のモチベーションを計りながら行動を促す対人支援技術であると教えて頂き、幾つかの実践演習をしました。
人の話を聞く際に気をつけるベーシング(相手の雰囲気、速度、言葉に合わせる)等を教えていただきましたので、初めてお会いした先生方と1対1で話をすること等、少しの緊張はありましたが楽しんで研修に参加することが出来ました。
園でも私生活でも、「この人とお話しがしたい。話していると安心する。」と言ってもらえる人になりたいと思います。
【篠原 松山 7名】
- 3月27日 大阪府私立幼稚園教育研究大会 分科会Ⅱ 第3分科会
-
2014.04.09
「子どもの急なトラブル(急変)~急な病気とケガのコツ」
今回の研修では、発熱児やけいれん、嘔吐、アナフィラキシーの対処法や子どもたちに起こり得る事故と対処法について、講義していただき、知識を深めることが出来ました。
「日頃から子どもたちの事を良く観察し、よくふれること」また「子どもの事故を予測し、予防すること」の重要性を改めて感じました。
今回学んだことを活かし、今後も子どもたちが安心できる的確な対応や事故の予防に努めたいと思います。
【上田 茅波 11名】
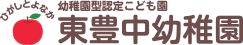

これからも子どもたちのよりよい育ちに繋がるよう、職員同士情報を共有していきたいと思います。
【姫島里佳 全員参加】