先生たちのポートフォリオ
- 8月25日 令和3年度若手保育者研修会
-
2021.09.17
- 8月20日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 第12回幼児教育実践学会
-
2021.09.17
今回は子どもたちの体力向上について取り組んだ事例の発表を聞きました。幼児期に経験する基本的な動き(28の動き)に着目し、子どもたちに足りない動きは何か具体的に考え、保育に取り入れ、環境を整えることで、子どもたちの遊び方にも変化が見られ、身体の発達にも変化が見られたことがわかりました。
子どもたちに必要な事は何かを明確にし、「楽しい」と思えるような動きを取り入れながら、子どもたちと沢山体を動かしていきたいと思います。
【宝珠山 場所:オンライン研修】
- 7月29日 近畿地区私立幼稚園教員研修大会 第3分科会「保護者会がなくても大丈夫?!」
-
2021.09.17
京都のある園の先生からの発表で、そこは元々保護者会の活動が多かったけれども近年保護者会をなくされたそうで、その中での工夫や苦労を話してくださりました。自園は行事等での保護者の担当・係等は少ない方かとは思いますが今後も園と保護者とで常に協力し合いながら、子どもを健やかに育てていきたいと思いました。
【天野:他2名参加 場所:WEB研修】
- 8月20日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 第12回幼児教育実践学会
-
2021.09.17
保育ドキュメンテーションとは、写真に言葉を添えたり動画を撮ったり活動中の子どもの様子を具体的に記録することで、活動を深めることができ、保育計画が立てやすくなることを改めて学びました。そして、保護者の方々にも、「せんせいにっき」や動画配信を通して、子どもたちの姿や幼稚園の様子をより知っていただけるよう、子どもの姿を見つめ記録し、発信していきたいです。
【小池 他1名参加 場所:オンライン研修】
- 8月20日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 第12回幼児教育実践学会
-
2021.09.17
研修を通して、日々の保育の中で子どもたち一つ一つの行動・言動を記録しておくことで、子どもたちが楽しめる環境づくりや、次の遊びに展開できるような援助ができて、とても大切なことだと感じました。写真に収めるだけではなく、文章にも残して振り返りができるようにしていきたいと思いました。
【西坂 場所:オンライン研修】
- 8月20日 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 第12回幼児教育実践学会
-
2021.09.17
今回の研修では3つの事例から、大人は子どもの姿を無意識に決めつけたり思い込んでしまったりすることが多く、子どもの本来の姿に気づけない時があるのだと学びました。また、より丁寧に子どもと関わり、寄り添い、保育者も余裕をもて向き合うことが大切だと学びました。
子どもの声に耳を傾け、想いを取り入れながら子ども主体となる保育ができるよう心掛けていきたいです。
【佐々木 場所:オンライン研修】
- 7月29日 第35回 近畿地区私立幼稚園教員研修大会 第1分科会「5歳児保育の本当に大切な事 ~いかに資質能力を育て、意欲を育み保護者・小学校に伝えるか~」
-
2021.09.17
大阪府私立幼稚園連盟の教育研究所が行っている第28次プロジェクトの研究発表を聞かせていただきました。
5歳の学びと育ちがなぜ大切なのか、そこで育てるべき資質能力とは何か、そしてそれが小学校へどのようにつながっていくかを学びました。園により保育形態は様々ですが環境の工夫や保育者の意図的な取り組みなど共通点も多くありました。今回のプロジェクトで見出された保育の本質について理解を深め、自園での実践にもつなげていきたいです。
【井上 他2名参加 場所:オンライン研修】
- 7月29日 第35回 近畿地区私立幼稚園教員研修大会 『新しい時代を伸びやかに生きるとは~園長のマネージメント能力と教員の資質向上について~』
-
2021.09.17
新しい時代を子どもたちが伸びやかに生きるためには、質の高い幼児教育と社会に開かれた教育課程の一体的推進を図ることが重要であるとのお話を聞かせていただきました。また、教員の資質向上のために持つ視点や方法について学びました。自園でも色々な先生が色々な分野でリーダーシップを発揮したり、教員自らが学びを進める環境を整えたり、仕事を通して人として育つ職員集団でありたいと思いました。
【井上 他2名参加 場所:オンライン研修】
- 7月29日 近畿地区私立幼稚園教員研修大会 特別講演「これからの幼児教育にむけて」
-
2021.09.17
幼児期に質の良い教育を受けることの大切さ、また環境を通しての教育の大切さを学びました。これからも子どものためにどういった保育環境を準備していくか、その準備した環境の中で子どもがどう育っていっているかを同僚の先生たちとたくさん話し合っていきたいと思います。
【天野:他2名参加 場所:WEB研修】
- 7月29日 近畿地区私立幼稚園教員研修大会第7分科会「無償化時代の認定こども園経営」
-
2021.09.17
近年の少子化、社会状況、子育てのあり方などの変化により、幼稚園から認定こども園に移行した園の様々な課題や現状について貴重な話を聞くことができました。どんな状況になっても子どもの育ち、保育の質が変わらず維持できるようにどの園も努力されており、とても刺激をうける内容でした。これからもよりよい職場環境や保育の充実に取り組んでいきたいです。
【右松:他2名参加 場所:WEB研修】
- 8月20日 第12回幼児教育実践学会口頭発表Ⅰ「保育者・園長が主体的に学び続けるための研修、研究、評価への取り組みについて」~学びを止めない~
-
2021.09.17
大阪府私立幼稚園連盟の教育研究委員会で取り組まれているさまざまな活動内容や研修再編への過程を聞きました。日々の保育の中で課題発言、計画、学び、実践、ふりかえりが園内で円滑に回っていることが大切であると学びました。これらを円滑に進めていく主任やミドルリーダーに必要な力が育つ研修を提供してくださっています。積極的に参加して学びを深め、園の資質向上と職員全体のチームワークづくりに役立てるようにしていきたいです。
【磯﨑 他1名参加 場所:web研修】
- 8月20日 おはよう!!「きょうはなにをしようかな」~子どもと一緒に創るわくわくする園庭~
-
2021.09.16
今回の研修から、園庭の環境構成や遊びを工夫することで子どもたちのわくわくや期待、「ようちえん大好き」という気持ちにつながるということを学ぶことができました。工夫としては、子どもたちが季節を感じることができるように5月にはこいのぼりをかざったり、6月の梅雨の時期には雨の音が聞けるように缶を置いたり、葉っぱを置いて浮かばせることを楽しめるようにするなど、「今日は何があるかな?」と思える環境づくりが大切だと思いました。自園でも、園庭は保育室までの道のりではじめに通る場所になるため、子どもの新しい発見やわくわくした気持ちにつながる工夫をさらに考えていきたいと思います。
【和多野:他8名参加:場所:Web研修】
- 8月20日第12回幼児教育実践学会 口頭発表Ⅰ「3歳児クラスの生活と異年齢交流での子どもたちの育ち」
-
2021.09.16
今回の研修では異年齢交流について学びました。異年齢の交流をすることで、子どもたちは子どもたち同士で刺激を受ける。年長さんに憧れをもつ子どもや、してもらって嬉しかったことを年下の子どもたちに伝えることができる場でもある。保育者が異年齢で交流できる場をつくり、異年齢保育ならではの関わりができるように努めていきたいです。
【濱田 他2名参加 場所:web研修】
- 8月20日 第12回幼児教育実践学会 口頭発表Ⅱ「子どもの主体的な活動としての遊びが充実するための環境を考える」
-
2021.09.16
今回は、子どもたちが主体的に活動し、充実して遊ぶための援助について学びました。
子ども一人ひとりが何に興味をもっているのかを読み取り、理解していくことで集団でも友だちとの関わりの中で自己発揮していけると学ぶことができました。
また、保育者が見通しをもつことで、子どもたちがより遊びを深められることも知りました。
子ども一人ひとりと丁寧に向き合い、主体性を引き出せる援助を実践していきたいです。
【齋藤:他2名参加 場所:WEB研修】
- 8月26日 幼稚園新規採用教員研修(第4回)₋リズム運動と実践の振り返り‐
-
2021.09.08
リズム運動では、音楽やリズムに合わせて身体を動かすことの楽しさを感じるための雰囲気づくりが大切であることを学びました。様々な種類のリズムを活用して子どもたちの「やってみたい」という意欲を引き出していきたいと思います。
実践の振り返りでは、4月からの自身の行動を客観視することで”できていなかったこと”が明確になり、2学期以降の課題に気づくことができました。子どもたちにとってより良い保育を行うために日々、自身の行動の振り返り・反省を大事にしていきたいと思います。
【名前 宗藤 :他2名参加 :場所 WEB研修(東豊中幼稚園)】
- 8月31日 令和3年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座 第3回
-
2021.09.01
今回の研修を通して、チームについてや園内研修のあり方について学ぶことが出来ました。チーム間でメンバーについてや課題の目標等をしっかりと共有して、より良いチーム作りに努めたいと思いました。また、年間を通して園内研修では、松(教育課程等の既にあるものの理解)、竹(子どもの育ち、行事計画と見直しなどの、今目の前にある問題)、梅(自園の理解、自己理解等の正解を求めない学び)の「松竹梅」を上手く織り交ぜながら園内研修を計画し、より充実したものにしていこうと思いました。
【馬渕:他1人参加 場所:大阪私学会館】
- 8月6日 幼稚園新規採用教員研修 第3回
-
2021.08.25
今回の研修では、子どもが困難を感じた時に「やってみよう」や「できた」などの自己肯定感を高める援助の必要性を学びました。
子どもたちが何につまずいているのか、子どもの行動を理解しながら環境を整えていきたいです。
【阿佐:他2名参加 場所:オンライン研修(東豊中幼稚園)】
- 7月28日 園内研修
-
2021.08.16
「1学期を振り返り、みんなで共有する」
「教育課程・年間指導計画について共通理解し、見直し・編成する」
学年ごとに毎月末行っている7月の子どもの様子の振り返りに加え、1学期の保育についての振り返りをしました。保育の中で意識して取り組んだことや、2学期にしていきたいことなどを学年で話し合い、他学年やフリーとも共有することで、職員全員で共通理解することができました。
教育課程・年間指導計画の見直しでは、子どもの姿や成長を考え、コロナ禍のおける援助や配慮についても加えて話し合いながら編成しました。振り返りや話し合いをしっかり行い、チーム力を高め、より良い保育が行えるようにしていきたいと思います。
【藤本 他34名参加:場所 東豊中幼稚園遊戯室】
- 7月20日 幼児教育人権教育研修 第1回
-
2021.08.06
今回の研修では、幼児期の段階から自分自身を大切にするとともに、相手を思いやることが将来の豊かな人間関係を築くためにいかに大事であるかを改めて学びました。
今後も子どもたちが、自分は大切にされている存在であることを実感したり、自分自身の良さや個性を自覚したりする経験を保育の中により多く取り入れていきたいと思います。
【宗藤:他2名参加 場所:WEB研修(東豊中幼稚園)】
- 7月16日 令和3年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座 第2回
-
2021.08.02
ファシリテーターの役割とは、自分の考えや主張を一方的に教えるのではなく、問題解決のために当事者が自ら納得できる成果や答えを見いだしたり、当事者の気づきや成長を促進させたりするプロセスに働きかけることだと学びました。
また、価値観の違いを面白いと思い、違いを受け容れることから関わりが深くなることも学びました。
職員でともに考え、ともに学んでいきながら、保育の向上に努めていきたいです。
【大野:他1名参加 場所:大阪私学会館】
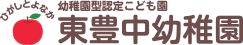

研修を通して「させる保育」ではなく、子どもたちが主体となって好きな遊び等を理解し、その遊びから保育活動として保育ができるような、「する保育」を心掛けることが大切だと学びました。
コーナー作りでは、子どもたちが「楽しい!」「もっとしたい!」と思えるようなことを、子どもたちの遊びを見ながら考えて、保育者も一緒に楽しめる環境構成をしていきたいです。
【西坂 他5名参加 場所:大阪私学会館】