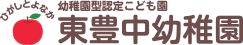先生たちのポートフォリオ
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.13
「オンラインによる公開保育の試み」 キーワード「保育の見直し」 コロナ渦で対面の研修や公開保育などが難しくなる中、公開保育の在り方について見直しや工夫をし、オンライン上で実践された事例を聞かせていただきました。発表やディスカッションを通して、これからの研修の在り方や参加する教職員の地域の幅が広がることなど、学びの選択肢がひろがる良い取り組みであるなと感じました。 また、オンラインでは、近隣だけでなく全国の教職員とつながり語り合うことができることや、小学校の先生など普段なかなか参加することが難しい先生方ともつながりを持ちながら幼児教育について学び合う機会が持てる可能性があることは、実施園にとっても、保育の質をさらに向上させていくきっかけにつながると思います。 保育の見直しや質向上などを含めて、教員の学びの意欲や意識が途絶えることのないように積極的に参加していきたいと思います。 そして、これからもオンライン活用の選択肢も残していきながらより充実した公開保育の実践や研修が進めていけたらと思いました。 他園の先生の実践されている保育を見ていただくことや、見ること、多くの先生方と意見交換や悩みなどを語り合えたりする機会は、現場の保育者にとって得難い時間であるのでこれからも積極的に職員の研修参加ができるよう進めていきたいです。 【右松:オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.12
「異年齢保育を通して、保育者同士の心のつながりを考える」
今回の発表を通して、同僚性を深めるためには、日ごろから意識的に笑顔で話すことや、相手を尊重したコミュニケーションを図ることが大切であることを改めて確認することができました。
経験年数に関わらず職員全体で対話しやすい雰囲気づくりや環境にし、それぞれが得意なことを活かせるチームプレイの保育を心掛けていきたいです。
【七種:他10名 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.12
今回の発表を通して、それぞれの子どもの発達段階や個性をしっかりと見極めた上で、子どもたちの言葉や言動に秘められた内面の育ちや気持ちを理解した上で、保育計画を考えたり進めたりする大切さを改めて感じました。
研修で得た知識や考え方をこれからの保育に活かしてより良い保育を行えるように取り組んでいこうと思います。
【馬渕:他1名参加 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.12
今回の発表を受けて、子ども一人ひとりの遊びのイメージが集団の遊びに影響を与えたり、集団の遊びのイメージが一人の子どもの遊びに影響を与えたりしながら、友だちとの関わりが増え、お互いに刺激し合いながら成長していくのだと感じました。
これからも、一人ひとりの成長段階や姿を理解し見守りながら遊びの中で子どもたちの力が発揮できるように保育を振り返ったり日々試行錯誤しながら遊びこめる環境ができるよう保育をしていきたいです。
【佐々木リ:他5名 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.12
「子どもと暮らすとは」~子どもの生活の中にある「ー」~
今回の発表で子どもたち自身が興味を持ち遊びこむことで、本人で気づく学びや日々の保育生活で生活リズムを自分たちで作る暮らしについて学びました。
これからも子どもたちと遊ぶことで見えてくる子どもの興味や気づきを大切にした保育を行っていきたいと思います。
【阿佐:オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.08
「カブトムシを育てて命に出会った4歳の発達」
今回の発表では、カブトムシを育てたことで命に対する思いの変化やカブトムシに出会ってからの子どもの姿について学ぶことができました。
命の大切さを知るのは言葉で伝えるよりも、子どもたち自身が身近に経験し、身についていくものであると改めて感じました。
これからも子ども主体で様々なことを経験し、心と体が共に成長したり学びにつなげることができるよう、保育をしていきたいと思います。
【佐々木レ:他10名参加 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.07
「ユニバーサルデザインの保育、教育を目指して」
~子どもの育ちをチームで支える園に~
子どもの気になる行動を観察し、個別の指導計画を作成するためのツール「CLM(チェックリストイン三重)」について学びました。
今回二つの事例から、「CLM」の大切さを知ることができました。
「CLM」を用いると、その子どもについて知ることが出来たり、特性を知ってその子にあった関わりができたりすることで、子どもたちの成長へとつながるとても良いと取り組みであると感じました。
また、特性のある子どもだけではなく、クラス全体で支援方法を共有することで子どもたちみんなで改めて他者の気持ちに気づいたり、知ったりすることができると知りました。今後保育をしていくなかで、クラスのみんなで大事なことについて理解を深めていけるような保育をしていきたいです。
【森:他4名 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.07
幼小接続に関する口頭発表に参加しました。
幼児教育では「環境を通して行う教育」小学校教育では「学習目標の到達に向かう教育」と、教育に対する捉え方に違いがありますが、幼稚園小学校の両教員が互いの教育内容を共有する機会を設け相互理解を深めることで、子どもが幼稚園から小学校へ就学する時になだらかに接続することができるという発表を聞きました。豊中市も幼保こ小で教職員が協議、連携を図る機会があるため、今回の学びを活かし、幼児教育と小学校教育の相互理解を各施設の教員同士で深めていきながら、子どもたちにとって無理のないなだらかな幼小接続がなされるように努めていきたいです。
【山本 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.07
「異年齢活動を通しての子どもの学びについて」
今回の発表では、異年齢活動を通し、子どもたちにどのような変化が見られたのか、また、保育者はどのように援助を行ったかを知ることができました。
家庭における「きょうだい関係」とは違った「異年齢」という環境で、子どもたちは困難を共に解決したり、楽しさを共有したりしながら、一人ひとり成長していました。
保育者として各学年に応じた援助を行うことで、年上の子どもからの一方向性の関わりではなく、多様な年代からの双方向性効果が得られるようにしていきたいと思います。
【宝珠山:他2名 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.07
「学びの連続性を考える」
~子ども理解を深め、遊びの過程から学びの芽生えや育ちを見つめる~
今回の発表では、なかなか遊び出せない子どもに対してどのようなアプローチをしていけばよいかについて学びを深めました。
一人ひとりの興味関心、問いに対して保育者が心を向け丁寧に見つめることで、子どもたちにとってより遊びたいと意欲が高まる環境づくりへ近づくことを再認識することができました。
子ども理解のため、今日を明日へ今週を来週へと繋げられるように意識し、学びや育ちの連続性を大切にしていきたいです。
【宗藤:他2名 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 口頭発表
-
2022.09.06
「新しい時代をのびやかに生きる」社会に開かれた質の高い幼児教育を あそびをつなぐ「わくわくコーディネーター」による実践 ~「子ども」「保育者」「家庭」を繋ぐ組織マネジメントの在り方について~ 今回の発表では、保育の様子を園全体で把握する為、各クラスの遊びの様子や担任の思いを総合的に把握し、発信する「わくわくコーディネーター」の取り組みについて事例を見ながら学びを深めました。 また、グループディスカッションでは、感じたことや、他園ではどのような取り組みをしているのかを話し合いました。 今回学んだことを活かしながら、これからも子どもの姿や担任・フリー教諭の思いを園全体で共有しながら、保育を行っていきたいと思います。
【金:他6名参加 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 基調講演3
-
2022.09.06
~子どもたちの豊かな学びを支える保育者を目指して~
今回の研修では、「子どもたちのウェルビーイング」とは何かを学ぶことができました。子ども一人ひとりが健康で安定した生活を実現できる状態でいられるよう保育者として、子どもたちが安心して思っていることを伝えられる、実現できるようなのびのびといい気持ちで過ごせる環境を作っていけるように今後も取り組んでいきたいと思います。
また、子どもの育ちを支える為には、同僚性が大切であるということを改めて考えることができました。
より良い保育を行っていけるよう保育者同士がお互いに思いやりをもって、伝えあいながら向上心をもって学び合うことができるよう努めていきたいと思います。
【馬場:他26名参加 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 基調講演2
-
2022.09.06
今回の研修では、子どもたちの非認知能力や主体性は環境によって育まれることを学びました。その環境とは、子どもが自分で想像したものに近づけられるよう、遊びを広げるきっかけを作るということだと知りました。
これからも主体性を育む上で、子ども自身で考えて、発見して、様々な経験ができるよう、子ども目線にたつことを大切にしながら保育をしていきたいと思います。
【築地:他26名参加 オンライン研修】
- 8月20日 第13回幼児教育実践学会 基調講演1
-
2022.09.06
~写真から学ぶ保育の環境構成スキルアップ~
「遊びひたる保育とは」「幼児と共に創造する保育環境を考える」
今回の研修では実際の事例や写真を通して、環境構成の大切さを学ぶことができました。
保育者が作る環境構成が、子どもたちの「やってみたい」を引き出すこと、また、子どもたちの遊びによって新たな環境ができることから、日々の子どもたちの姿を振り返り、子どもたちが楽しめる環境づくりに努めていきたいと思います。
【濱田:他26名参加 オンライン研修】
- 7月12日 令和4年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座
-
2022.09.06
自ら学び、共に育ちあえる主体的で対話的なチーム作りを目指してファシリテーションやリーダーシップの在り方を理解し実践につなげていけるよう学びを深めています。
第3回はチームとは何かということを改めて考えながら、チームのあり方を知り、今のチームの現状や目標を知るための手立てを知るとともに、チーミングについて学びを深めました。
まずはお互いを知り合うことから始め、会話ではなく「対話」がなされる関係性を築いてくことが良いチーム作りの土台になるということを念頭に、講義で教えていただいたことや、ワークを取り入れ、園でのチーム力向上に活かしていくことができるよう、取り組んでいきたいです。
【右松:他2名参加 大阪私学会館】
- 8月29日 研修名:東豊中幼稚園について考えてみよう(園内研修)
-
2022.09.05
今回の研修では、幼稚園のルールの振り返りや、園内の様々な場所について考え、理解を深めることができました。園内図を用いて可視化することで、それぞれの場所について意見を共有でき、疑問を解決することができました。
幼稚園のルールや施設について理解を深めることができたので、それぞれの場所での環境構成を工夫し、子どもたちがより園生活を楽しめるよう、努めていきたいです。
【名前 松枝:他4名参加 場所:東豊中幼稚園】
- 8月24日 研修名:令和4年度幼稚園新規採用教員研修第5回 ーセルフマネジメント2~メンタルマネジメント~ー ー指導案・指導計画の作成ー
-
2022.08.31
今回の研修では、健康の土台づくりは食事・運動・睡眠であることを学びました。また、指導案・指導計画を作成する時の順序や子どもの姿・遊びを見るポイントについて理解を深めることができました。
今回学んだことを活かして、子どもが見通しをもったり、遊びを楽しめたりするように声かけ・援助をしていきたいと思います。
【名前 髙橋:他4名参加 場所:大阪府教育センター/オンライン研修】
- 8月1日 研修名:令和4年度幼稚園新規採用教員研修第4回 -リズム運動- -これまでの実践を振り返るー
-
2022.08.15
今回の研修では、これまでの学びや実践の振り返りを行いました。他園で働く保育者の方々と日々の保育での気付きや学びを共有し合う中で、子どもとの関わり方や今後の目標について改めて考えることができました。
今後は、子どもとの関わりをヒントに、園全体の子ども達が楽しめるような環境づくりに努めていきたいです。
【名前 松下:他4名参加 場所:大阪教育センター/オンライン研修】
- 7月20日 食育と食物アレルギーへの対応について
-
2022.07.22
今回の研修では、幼児期における食育の重要性や、食物アレルギー発症時の対応について学びました。
コロナ禍での食の楽しみ方を考えたり、実施にエピペン(練習用)を使って使用方法を知ることができました。
今後も子どもの安全を考えた食育を行い、適切な対応ができるよう努めていきたいと思います。
【 斎明寺 大阪府教育センター 】
- 7月8日 新任研修 幼稚園の1日のスケジュール(園内研修)
-
2022.07.11
今回の研修では、園の1日のスケジュールについて、学びました。
園の1日の流れを知ることにより、子どもが1日の中でどのようなことを行っているのか、保育者として配慮する点などを詳しく学ぶことができました。
担任をもった際のポイントについて学んだため、今後先輩方の工夫している点を参考にしつつ、自分で考えながら楽しんで保育を行えるよう、努めていきたいです。
【名前 髙橋:他4名参加 場所:東豊中幼稚園】