先生たちのポートフォリオ
- 7月20日 幼児教育人権教育研修 第1回
-
2021.08.06
- 7月16日 令和3年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座 第2回
-
2021.08.02
ファシリテーターの役割とは、自分の考えや主張を一方的に教えるのではなく、問題解決のために当事者が自ら納得できる成果や答えを見いだしたり、当事者の気づきや成長を促進させたりするプロセスに働きかけることだと学びました。
また、価値観の違いを面白いと思い、違いを受け容れることから関わりが深くなることも学びました。
職員でともに考え、ともに学んでいきながら、保育の向上に努めていきたいです。
【大野:他1名参加 場所:大阪私学会館】
- 7月26日 令和3年度幼児教育アドバイザー育成研修 第3回
-
2021.07.27
今回は非認知的能力の重要性とそれを育む援助の在り方について、子ども理解とも関連させて学びました。
教育要領の改訂に伴い、知識(認知的能力)だけではなく、生きる力となる「非認知的能力」を育む教育、保育がより重要視されるようになりました。
非認知的能力は教えられることでは身につかず、経験の中で自ら気づき、身につく力ですが、これまで行ってきた「環境を通した保育」を振り返りながら日々保育していきたいです。
【山本:場所 オンライン研修(東豊中幼稚園)】
- 7月1日 令和3年度幼児教育アドバイザー育成研修 第2回
-
2021.07.08
今回は乳幼児期の発達等の状況を踏まえ、子どもにふさわしい援助や指導の在り方を学びました。
各園によって保育方針等が異なるため、教員間で教育課程や保育で大切にしていること等を十分に共通理解し、「子ども主体」を前提に組織的に保育活動を行うことが大切であると再認識することができました。
今回の学びを日々の保育に活かしてきたいです。
【山本 場所:オンライン研修(東豊中幼稚園)】
- 6月30日 令和3年度ファシリテーション・リーダーシップ連続講座 第1回
-
2021.07.01
今回は、ファシリテーション・リーダーシップのあり方を理解し、チームに良い変革を起こすことを目的とした研修を通して、様々な学びがありました。職員間でのやりとりや後輩への指導の際に、決めつけた言い方をするのではなく、助言やアドバイス・一緒に考えられるような伝え方をすることの大切さを改めて感じました。職員間のコミュニケーションを円滑に行い、話し合いを深めることで、保育の質の向上に努めたいと思います。
【馬渕:他1名参加 場所:大阪私学会館】
- 6月25日 ちゃいるどネット 人権保育講座「一人ひとりを大事にする幼児のクラスづくりコース」
-
2021.06.30
今回の研修では、実践報告を通してクラスの集団づくりにおいて大切なことを学ぶことができました。
クラスづくりでは、クラスの「気になる子」を中心に捉え、その子と周囲の子がいきいきと過ごせるクラスの価値観を考えていくことが重要であることを学びました。
保育者自身の価値観や子どもの言動への反応を再度見直し、一人ひとりの子ども理解に努めながらクラスづくりを行っていきたいと思います。
【齋藤 他2名参加:場所 ドーンセンター】
- 6月5日 園内研修
-
2021.06.08
『お互いを知り合いながら、チームの仲を深めよう』
今年度初回の園内研修では、ともに仕事をしている先輩・後輩と楽しい会話をしながらコミュニケーションをとることができ、とても良い時間になりました。同僚の性格の傾向を知ることもでき、自分の好きなこと・苦手なことを互いに伝え合うことで、お互いを知ることができ、職員の仲も深まったように思います。そしてその後、園の保育方針について確認し、話し合いをしました。
職員同士協力しながらより良い保育ができるよう努めていきたいと思います。
【松山 他35名参加 東豊中幼稚園遊戯室】
- 5月27日 令和3年度幼児教育アドバイザー育成研修 第1回
-
2021.05.31
今回は、国立教育研究所の調査官の方から、今日の幼児教育をめぐる状況や幼稚園教育の基本、また、教育課程や記録、学校評価の役割についての講義に参加しました。
感染症対策や保育ニーズの変移など、常に変化する保育現場ですが、幼児教育の基本に変わりはないため、教育課程や記録、学校評価等を活用しながらより良い保育を行えるように、今回の学びを生かしていきたいです。
【山本 オンライン研修】
- 5月21日 「幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領をふまえた子ども理解」「食物と食物アレルギーへの対応」
-
2021.05.31
今回の研修では、アレルギー対応や緊急時の判断・役割、また子ども理解について学びました。エピペンの使い方や、緊急時での役割分担が子どもの命を守る大切な役割であると思いました。また、子どもと深く関わり、言葉掛けを重ねていくことから信頼関係に繋がっていくと学びました。改めて子どもと同じ目線で物事を考えることを意識していきたいです。
【濱田 他2名参加 場所:東豊中幼稚園(web研修)】
- 5月15日・16日 日本保育学会第74回大会
-
2021.05.18
日本保育学会として初めてのオンライン形式による学会に参加しました。
2日間に渡る講演や口頭発表、シンポジウムを通して、保育の様々な視点に着目した研究を学ぶことができました。
今回の学びを今後の保育に生かしていきたいです。
【山本 他2名参加 ZOOM(オンライン開催)】
- 5月8日 令和3年度 フレーベル祭 研修会 (大私幼)
-
2021.05.12
『主体的で対話的な保育を創造する ~多様な個が生きる場を目指して~』
今回の研修では、他園の主体的で対話的な保育活動の例をたくさん教えていただきました。自園でも子どもたちが主体的に活動することを大事にしていますが他にも様々な方法があることを学ぶことができました。これからも子どもの発信・気づきをしっかりキャッチして広げたり、子どもの疑問を一緒に考えたりすることを大切にしていきたいと思います。また、子どもたちが自分たちで考えて自分たちで決めて楽しむ保育ができるよう環境を整えていきたいと思いました。
【藤田 他32名参加 オンライン研修】
- 4月30日 第1回幼稚園新規採用教員研修「セルフマネジメント1~働くための基本的スキル~」
-
2021.05.11
今回の研修では、ビジネスマナーやタイムマネジメント、自己改善力などの基本となる保育者として重要なことを学びました。子どもたちの安全のためにも「報告・連絡・相談」などの連携を大切にしようと感じました。日々の保育を振り返り、より良い保育を行うために学びをを深めていきたいと思います。
【阿佐 他2名参加 場所:東豊中幼稚園】
- 4月19日 YMCA講習
-
2021.05.06
運動あそびにおける子どもへの補助や、様々な運動遊びについてYMCAのリーダーから学ばせていただきました。
実際に、マット運動・跳び箱・鉄棒を行い、それぞれに応じた補助を体験することで子どもの目線に立って考えることができました。そして、より具体的なイメージがつき、基本から展開性のある動きまで学ぶことができました。
これからは、子どもの安全を確保した環境設定のうえ、適切な補助法を実践していきたいと思います。
【築地 他18名参加 場所:東豊中幼稚園】
- 3月23日 第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会「クライシス・コミュニケーション~大津市における対応事例~」
-
2021.04.16
2019年5月に大津市で起こった、散歩中の保育園児に車が衝突した事故の当事者である、保育園副理事長からの話でした。当日事故が起こってから、自分たちが状況把握する前にマスコミが情報を発信していたこと、記者会見・保護者への説明会でどのように対応したかなど、実際の経験を話してくださりました。研修を受け、普段から職員間での連携体制を強くしておいたり、特に園外へ行く時には危険な箇所の確認を事前にしておいたり様々な可能性を想定しておくことが重要だと感じました。
【天野 他9名参加 場所:WEB研修(東豊中幼稚園)】
- 3月31日 マナー研修
-
2021.04.08
新年度を迎えるにあたって、社会人としてのマナーを再認識するために、マナー研修を受けさせていただきました。今まで何気なくしていたことが誤っていることだと気付くことができ、自分の言動や行動を見直す機会になりました。今回の研修をこれからに活かし、様々な人との気持ちの良いコミュニケーションを心掛けていきたいです。
【朝倉:他20名 場所:東豊中幼稚園(遊戯室)】
- 3月23日 第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会「運動あそび」
-
2021.04.08
今回は運動遊びと、そのルールの中に込められた3つのねらいについて学ばせていただきました。①豊富な運動量②子ども同士の関わり合い③達成感・失敗の経験がねらいだと知りました。また、②では、考える力や葛藤、戸惑い、判断に迷うなどの経験ができるということを学ぶことができました。これからの保育では、遊びから学ぶことを大切にしながら、今回知った運動遊びも取り入れていきたいと思います。
【築地 場所:Web研修】
- 令和2年度第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会「子どもの想いをつなぐ遊びの環境を考える」
-
2021.04.02
今回の研修では、子どもの姿と保育者のねらいや願いを踏まえた環境構成について学びました。子どもの想いに寄り添いそして私たち保育者のねらいを合わせた保育を行うためには、日々の子どもの興味関心、子どもが「やりたい」と思っていることを捉えるということが大切であると思いました。今回の研修を終え、子どもたちの想いや、興味関心を大切にした環境構成を考え、保育していきたいです。
【名前:和多野 場所:Web研修】
- 3月23日 第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会 [保育の記録・可視化・発信の重要性~ポイントと実際の事例を通して~」
-
2021.04.02
この研修を受けて「どんな遊びが楽しいか」ばかりを考えるのではなく、子どもたちの何気ない疑問、興味を引き出して遊びに発展させることが大切だと感じました。そこで子どもたちにとっての学びを読み解き、対話と喜びをもとに質の高い保育の実践に繋げていきたいと思いました。しかし子どもたちの「やってみたい!」ことの中に安全性、園での決まりを平行して考えて危険のないように保育者同士で話し合い、共有することも重要だと思いました。
【西坂:他29名 場所:WEB研修】
- 3月16日 第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会 「こども発見」
-
2021.04.02
今回の研修では、子どもとの関わりを振り返り、子どもを理解するために必要なことを学びました。子どもと同じ目線で物事を捉える大切さや、子どもを様々な角度から見つめる大切さを改めて感じました。目の前にいる子ども一人ひとりの個性や考え方を理解するためにも、相手の立場になって考えることをより意識していきたいと思います。
【阿佐:他2名参加 場所:WEB研修(東豊中幼稚園)】
- 3月22日 第63回大阪府私立幼稚園教育研究大会 「保育ソーシャルワークのすすめ①」
-
2021.04.02
今回の研修では、子どもを取り巻く環境における課題を知るとともに保育ソーシャルワークの考え方や大切にしている視点、また保育ソーシャルワークの支援の構造について学びました。保育者が聴く姿勢を大切にすることは一人ひとりの強み(=ストレングス)に気づくことに繋がり、その強みが子どもにとって大きな自信になるということを知りました。自分のことも相手のことも認め、互いの強みを最大に発揮できるような環境づくりに努めていきたいと思います。
【宗藤:他2名参加 場所:WEB研修(東豊中幼稚園)】
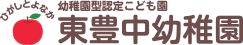



今後も子どもたちが、自分は大切にされている存在であることを実感したり、自分自身の良さや個性を自覚したりする経験を保育の中により多く取り入れていきたいと思います。
【宗藤:他2名参加 場所:WEB研修(東豊中幼稚園)】